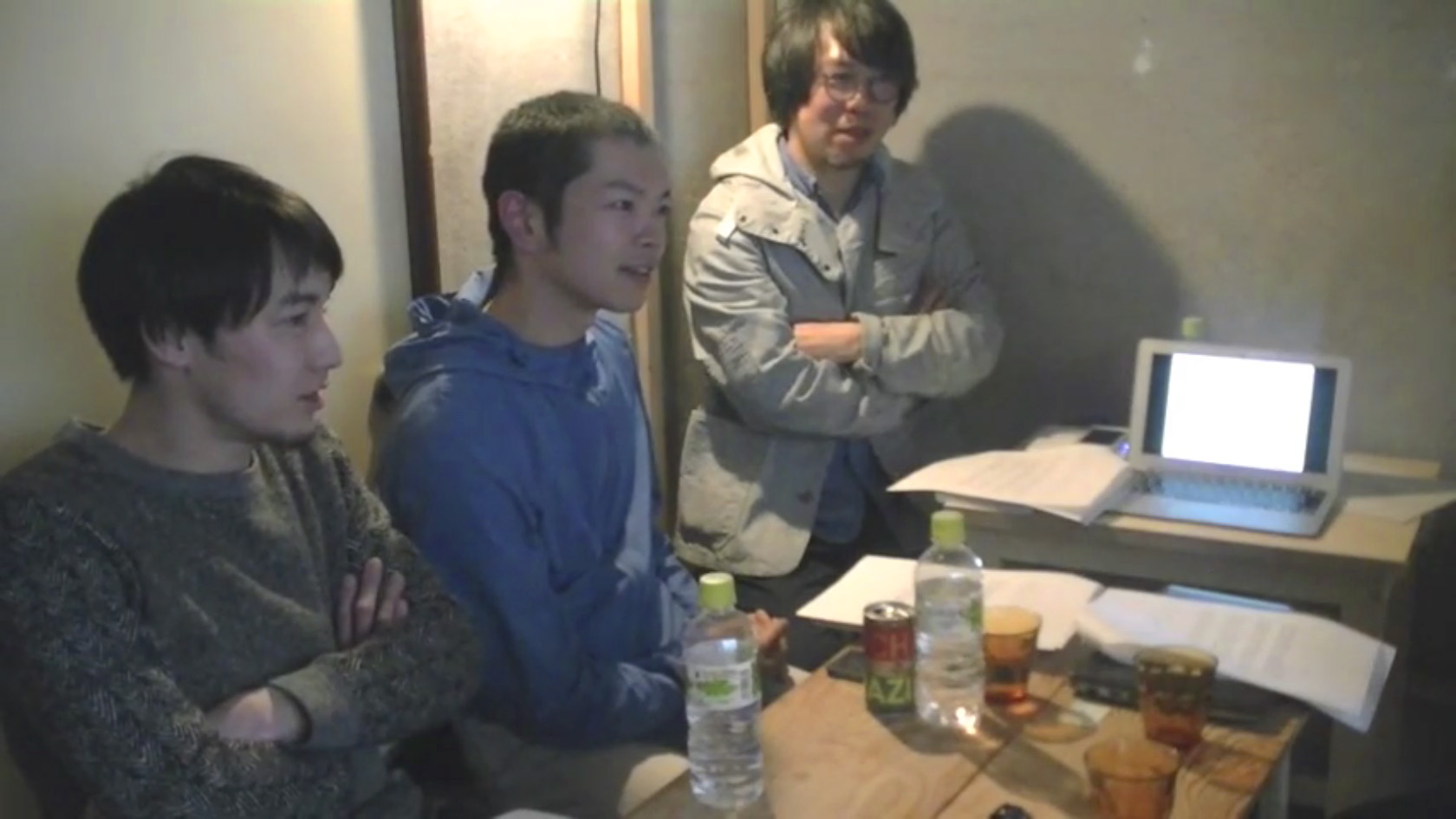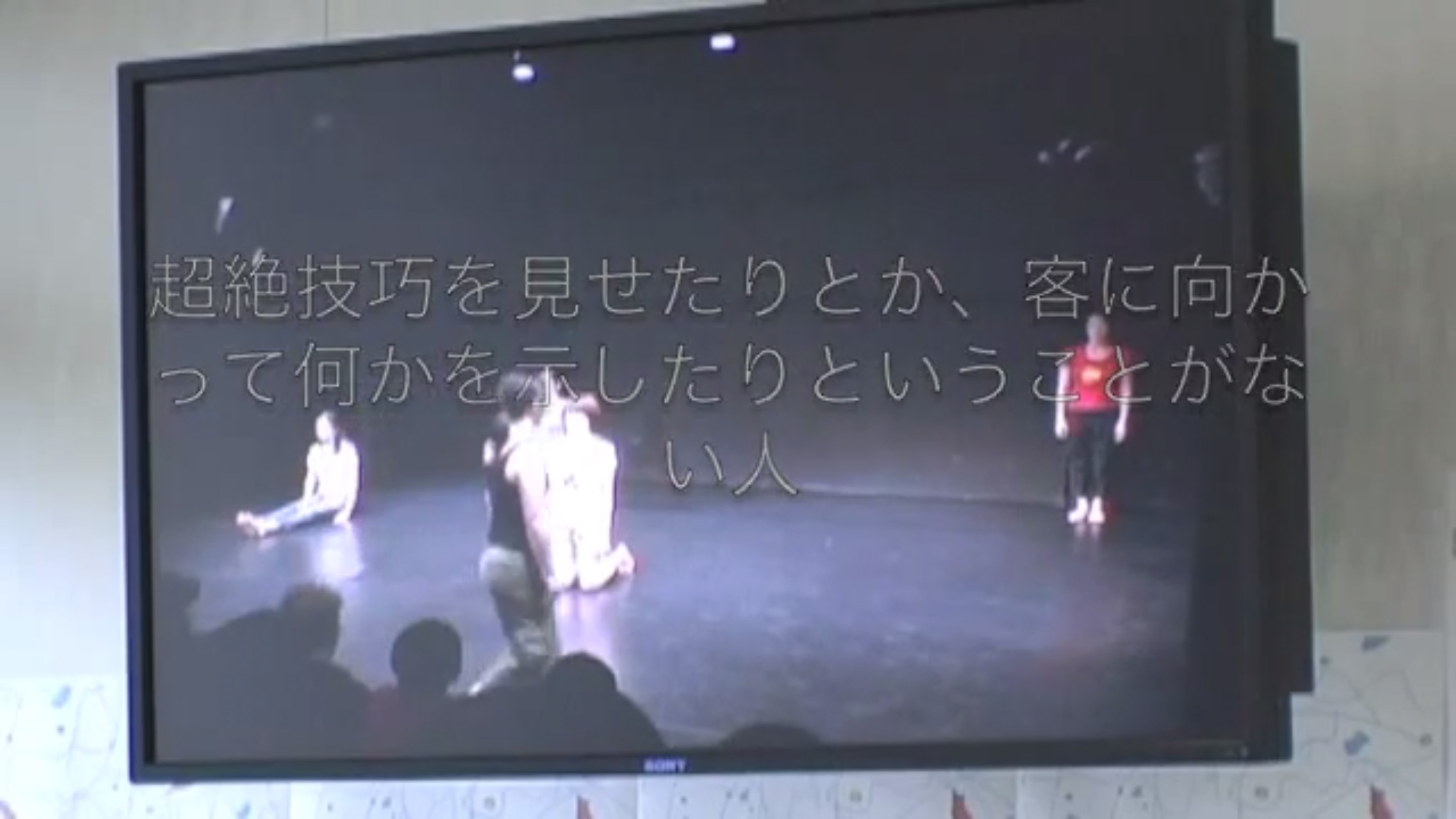2017/06/12
BONUSは今年度「ワークショップ」を掘り下げていきます。
神村恵、篠田千明、砂連尾理という3人の作家に次のテーマを渡しました。
「ダンス上演のオルタナティヴとなるワークショップを発明し、実践してください」
このテーマに基づいて、3人の作家を中心に、大小様々な企画を進めていきます。大きいイベントとしては、
- 7/9 研究会
- 1/28 イベント
を用意しています。(いずれも会場は京都造形芸術大学になる予定です)
「ワークショップ」を考察・実践するにあたって、今年の2-3月に、各分野の専門家にインタビューを行いました。(インタビューとそのコンテンツ化については京都造形芸術大学舞台芸術センターの助成を受け、実現しました。)
昨年はBONUSでもワークショップを何度か実施しました。その中で手塚夏子さんに取り組みを振り返ってもらいました。長谷川寧さんからは『ENIAC』や『Attack On Dance』で取り上げた「ダンサー」という存在についてお聞きし、またアーキタンツというダンススタジオに集う方たち(近藤美緒さん、井原恵さん、梶田留以さん)からもお話を聞いて、今日本のダンサーたちが置かれている状況について考察しました。特にワークショップを考えるために教える/学ぶ環境がどうなっているのかを知りたかったからです。堤康彦さんと石井路子さんからは、教育現場にダンスや演劇が導入される際に起こる摩擦や課題、またその価値について教えてもらいました。鈴木励滋さんはカプカプという作業所の所長ですが、舞台芸術に詳しくレビューを書くこともある方です。その鈴木さんが自分運営する喫茶店を演劇になぞらえていることに興味を持ち、喫茶カプカプを訪問したのがきっかけです。社会の中にどんな芸術的な知が求められているのかを2人が話し合いました。あと、3人の作家とも「ワークショップ」をめぐり話し合いをしました。それもコンテンツにしていきます。今後も、インタビューの活動は続けていきますが、まとまり次第、随時公開するつもりです。
インタビューズ
「ワークショップ」が作る未来のダンス
ワークショップの方法をめぐって
① 手塚夏子 「ワークショップあるいは社会を作るための知恵」
ダンサーの生態学
② 長谷川寧「「ダンサー」という謎の存在 長谷川寧と『ENIAC』と
③ 近藤美緒、井原恵、梶田留以「アーキタンツに集う3人のダンサーに聞く 日本でバレエ(ダンス)を踊るということ」
教育現場と舞台芸術の交点で起きていること
④ 堤泰彦「ダンス・ワークショップは子どもたちと何をしてきたのか 「芸術家と子どもたち」が見てきた「ダンス」」
⑤ 石井路子「タイトル未定」
オルタナティヴな場の創造に関して
3人の作家の考えるワークショップの現在と未来
ところで、なぜ「ワークショップ」を取り上げるのか? そして、なぜ「ダンス上演のオルタナティヴ」をワークショップに求めるのか? それほど長くないテキストを書き、そのあたりことをまとめてみました。
「ワークショップ」をめぐるノート
テキスト=木村覚
観客が暗がりから解き放たれる時
──パフォーマーと観客の関係の一方向性という限界を超えるものとして「ワークショップ」を構想できないか
劇場にいながら、虚しい思いを抱くことがある。舞台上のパフォーマーと観客とが明らかな出会い損ないをしている気がする時だ。
劇場はしばしば観客を受け身の存在にする。観客は黙して目の前の出来事を全面的に受け止めなければならない。舞台に上がったり、演者と対話することは、許されない。客席に乱入するタイプのダンサーでも、それは変わらない。激しく運動しながら客席をうろつき、観客の髪をつかんだり、時には観客を押し倒したり、観客のメガネを奪ったりする。この時、パフォーマーが観客に触れることが、両者の関係を変える誘いの合図かと、微かな(役割を変化させる)期待が胸に高まる。しかし、その高まりはあっさりしぼんでしまう。ダンサーの行為は、観客に働きかけてはいるものの、観客を能動的にするのではなく、反対に観客を石にする。黙って観客はダンサーのされるがままになる。暗がりから観客をレスキューしてくれるわけではなかったか、と切なくなる。
そうか、私はどこかで、観客である自分を解放してくれる誰かを探していたのだ。そんなことに、こういう時、気づかされる。
不思議なことに、素晴らしい公演に巡りあう時、大抵私は物思いにふけっている。公演が指し示すことに全く意識を傾けていないというわけではないのだけれども、何かを指し示す身振りが私の記憶を揺さぶり、心中では舞台で行われていることとは別の出来事が渦を巻く。この状態こそ、私にとって最良の上演体験である。そこでは、観客は単なる舞台の監視人であることから解放され、空想の翼を上下させる幾分か主体的な存在になっている。舞台との対話が生まれる状態というのは、こうした主体となった観客の存在無くしてはあり得ないだろう。しかし、この観客はまだ、無邪気だ。勝手に物思いに耽る自由を得たというだけだ。
観客というものは、こうして、無邪気な存在でいるために、お金を払って社会から逃避しているのだ。
舞台を照らす光は、照らされてない場所を隠す。客席はそうして、有って無きが如し場所として機能する。暗がりでは人は自由な空想を生きる。寝ることもできるし、見てみないふりをすることもできる。しかし、そこに光を当ててみよう。すると、そこにはいないはずの人がいる。「沈黙」が無ではないように、暗がりの観客は隠されているけれども、暗がりにちゃんと存在しているのだ。
ワークショップの場は、まさに「沈黙」の音を聞くことであり、暗がりを消去することであり、隠されていた観客が言葉と行動を持つことである。まるで観客にこの可能性を意識させないように、劇場の構造は機能しているかのようだ。固定された客席、数段高いところに位置された舞台。プロセニアムアーチで隔てられた二つの空間を強引に一つにしてしまおう。すると観客は言葉と行動を求められる。観客の能動性が発動させられる。
ここでは誰もが傍観者ではいられない。ここでは誰もが場の参与者に自ずとなる。囚人のような存在、出来事の部外者ではなくなり、責任が稼働し、自由と法則が生まれ、誰もがその場における「遂行者」となる。
さて、そこでは、現場に対して超越的な座に立つことはできない。場の内部に入ってしまうと場の外から中を批評することができなくなる。その時、批評はどう機能するのか、さて、このことは一つの大きな懸案事項となる。
[補足。もちろん能動的な観客は存在可能であろうし、また優れた上演というものには、能動的な観客を創造する仕掛けが含まれていると筆者は信じている。(まさに、今回依頼する3人の作家たちの上演で何度ぼくは能動的な観客であったことだろう。)例えば、ランシエールはそうした観客像のもとに観客という存在を積極的に捉えている。「連結し分離するこの能力こそ、観客の解放、すなわち観客としての我々ひとりひとりの解放が存している。観客であることは、能動性へと変えられなければならないような受動的な状態なのではない。それはわれわれにとって正常な状況なのである。われわれは、自分が見ているものを自分が見たもの、言ったこと、そして夢見たことに絶えず結びつける観客として学び、教え、行動し、そしてまた認識するのである。特権的な形式もなければ、特権的な出発点もない。いたるところに出発点、交差点、結節点があり、われわれが何か新しいことを学ぶことを可能にしてくれる。ただし、それが可能となるのは、第一に根源的な距離、第二に役割の分担、そして第三に領域間の境界を拒絶するという条件においてである。」(ジャック・ランシエール『解放された観客』梶田裕訳、法政大学出版局、2013、pp. 23-24)それは、上記の筆者のテキストにおける「物思いにふけっている」観客と似ている。だから劇場の従来型の上演で十分だ、という結論ではない道を筆者は探ってみたい。ランシエールの言葉を借りて「いたるところに出発点」があるというのならば、それはワークショップの極端に物理的距離が取り払われてしまう場所においても、能動的な観客は可能だろう。それは誰もがその場に主体的に参与しつつ、同時に、自分の判断や行動を認識しそこから学びをうる観客である。私たちは、社会において傍観者ではいられない。SNSで社会へ向けた批評が誰でも容易に可能になった。批評するとは一旦社会の外部に立つことを意味するならば、誰もが容易に社会の外部に立てる世の中になったというわけだ。だからこそ、重要なのは社会の内部に身を置くことなのではないだろうか。誰もが社会を運営するプレイヤーであり、社会を認識する批評家であり、プレイヤーであると同時に批評家であるはずである。]
集団的創造としての「ワークショップ」(ハルプリンについて)
──「集団的創造」を志向するハルプリンの方法から今日得るものはないのか
ワークショップの潜在的な可能性を考える上で、建築家のローレンス・ハルプリンが振付家の妻(アンナ・ハルプリン)や仲間たちと進めてきた方法は、一瞥しておくべきもののように思われる。ハルプリンは、ワークショップを「集団的創造」の場として捉えていた。その背景にあるのは、集団に生きる個人の疎外感だった。
「今日の世界における大きな問題の1つに疎外感の増大がある。それは家族を崩壊させ、そして個人を他の人から、集団から、政治や権力の中心からも孤立させる。
疎外感は自分の人生の重大な意思決定が、現実的にはその人個人の力ではどうにもならないという気持ちから起こってくるのが普通である。どこかで意思決定が自分達の一度も会ったことのない、一度も話すことの出来ない、いずれにしろ聞く耳を持たない、孤立した、のっぺらぼうの人間グループによってなされていると感じられるのである。」(ハルプリン、バーンズ、p. 19)
そこで、ハルプリンは多様性を認める方法の開発が必要であると訴え、自ら「テイク・パート・プロセス」というやり方を提唱した。それはRSVPサイクルと呼ばれ「このモデルは、構造的、線形的というより、むしろ関連的、環状的である。即ち、順序や到達目標ではなく進行や経過が強調され、機会あるいは道具または単なる生産物の受取人としてではなく、参加者としての人々に焦点が合わされる。」(ハルプリン、バーンズ、p. 32)としている。
このことは、ワークショップという空間を能動/受動、与えるものと受けとるものといった関係に固定させずに、集うもの皆がその場の参加者であるような状態を目標とし、それによって生まれる力がワークショップを行う目的への最良のものとなると考える、そうした「ワークショップ」観がベースになっているということだろう。
ワークショップを教師が生徒に一方的に教授するのではなく、集まった全ての者の力がきちんとその場に発揮されるよう場を仕立てること。ワークショップを考えることは、教育を考えることであり、その場に集ったものたちが構成するコミュニティのあり方を考えることである。
参考図書:ローレンス・ハルプリン、ジム・バーンズ『集団的創造の開発』(杉尾伸太郎、杉尾邦江訳、牧野出版、1989)
参加型アートの一形態としての「ワークショップ」の可能性とその課題
──観客が参加の状態になることで起きる課題とは何か
ところで、参加者の持っていないアイディアや技を、それを持っているアーティストが伝授するといったトップダウン式の関係性になりがちなワークショップから脱して、参加者の主体性を引き出そうとするときに、気をつけなければならないのは、「参加者の主体性を引き出す」アーティストの行いが、その狙いとは正反対に、参加者の主体性を形骸化させ、主体性を奪う結果になる場合がある、ということである。この点は(避けることは容易ではないが)注意を向けるべきだろう。美術批評家のクレア・ビショップは『人工地獄』(2012、邦訳2016)の中で、20世紀以降の参加型アートの歴史を紐解きつつ、今日的な課題を解明する中で、非芸術家が作品創作に参加することが非芸術家である参加者の主体性の遂行には直結しないと指摘した。ビショップはこう述べる。
「鑑賞者について言えば、次のように変化を説明しうるだろう。まず、(「プロセニアム」を統制する前衛のアーティストに向けた敵対行為として表される)役割を要求する鑑賞者。そして、アーティストが彼らのために創案した新奇な体験への服従を享受する鑑賞者。次に、協働して表現を創造することを求められる鑑賞者(彼らはときに、その関与によって報酬を受けることさえある)。これは、鑑賞者の能動性と行為主体性が次第に顕在化していく壮大な物語というふうに考えられる。しかし私たちはこれを、アーティストの意志への自発的な従属が次第に強まっていく物語、およびサービス産業における人体の商品化の物語として捉えることもできるだろう(なぜなら、自発的な参加は無報酬の参加でもあるためだ)。そしてこの物語は明らかに、民主主義そのものが辿った厄介な末路と並行関係にある。承認欲求や表象=代理、同意の上での自己イメージの消費(芸術作品、あるいは「フェイスブック」や「フリッカー」、リアリティー番組)など、この「項(term)」は常に参加と深く関係しているのだ。」(ビショップ、pp. 421-422)
ビショップがここで扱っているのは主として美術史の文脈における「参加」の歴史と課題であるけれども、投げかけている問題には芸術のジャンルの枠を超えた射程がある。アントニー・ゴームリー『ワン・アンド・アザー』を例に挙げる。一回一時間、市民メンバーに占有してもらう舞台をトラファルガー広場に用意し、市民は思いのままの行為を行い、それはストリーム配信された。ビショップはこうした参加を「ツイッター・アート」と批判した『ガーディアン』紙を受けて、「誰もがあらゆる人々に向けて意見を発信できる世界にあって、私たちが直面しているのは大衆への権限付与ではなく、陳腐化したエゴの垂れ流しである。スペクタクルへの抵抗どころではなく、参加はいまやスペクタクルと完全に一体化しているのだ。」(ビショップ、p. 422)
ビショップはそこで、ボルタンスキーとシャペロの『新しい資本主義の精神』で論じられた「芸術家的批判」と「社会的批判」の緊張関係を保つことの必要性を訴える(ランシエールはすでに『解放された観客』(2008)でボルタンスキーとシャペロのこの議論を取り上げている)。2つの「批判」はともに資本主義を批判する2つの異なる立場である。「芸術家的批判」は、ものや人や感情を脱魔法化し、非権威化する源泉としての資本主義、また人間の自由、自律性、創造性を抑圧する源泉としての資本主義を批判し、芸術家の自由を尊重する立場を指す。「社会的批判」は、社会主義やマルクス主義に鼓舞された立場で、非道徳性ないし道徳的中立性を否定し、個人主義を否定し、芸術家のエゴイスムを否定する。ビショップは、個人と集団、作者と観客、能動と受動、現実の生と芸術といった二つが緊張を残しつつ、互いを批判しつつ、共存している状態が、「水際立つプロジェクト」の条件であるとするのである。
参加する市民は、アートワールドの閉じた生産と消費の自己運動に自らの力を貸すだけになってしまうのか、それとも、自分たちの社会を考え、社会の膠着している病巣を突き止め、原因への処方箋を知るのに、アートの力を利用するのか、いや、そこからさらに進んで、社会の見方を切り替えるアートの力を市民が体感することで、アートの不思議がその不思議さを温存しつつ社会の内部に座を確保することになるのか。
参考図書:クレア・ビショップ『人工地獄』(大森俊克訳、フィルムアート社、2016)、ジャック・ランシエール『解放された観客』(梶田裕訳、法政大学出版局、2013)
観客が自治的な集団の場を起こすための「ワークショップ」
再度、ビショップの言葉を借りてみよう。
「参加型アートにおいて鑑賞者を能動化させようと欲することは、すなわち支配的なイデオロギーの戒律が──消費資本主義、全体主義的な社会主義体制、軍事独裁政権など、いずれであろうと──もたらす疎外状態から、彼ら〔鑑賞者〕を解放させようという希求を意味している。この前提の上で、参加型アートはソーシャル・エンゲージメントの結びつきによる自治的な集団の場を回復させ、生起させようとする。」(ビショップ、p. 418)
「参加」が気づけば「搾取」になってしまう権力の構図を回避し、集団の場を、しかも自治の場を用意すること。ビショップは参加型アートの目的をこの点に見ている。筆者もここに「ワークショップ」の目的を据えてみたい。自分も含めた観客こそが鑑賞のコンテンツになるアートの場に、観客は体のみならず意思をも持ち込む。この形式はどうしたら生まれるのか。アーティストに、非専門的なアートの参与者に、このことを考えてもらう場に集ってもらう。今年度のBONUSは、このことに集中しようと思う。
参考図書:クレア・ビショップ『人工地獄』(大森俊克訳、フィルムアート社、2016)