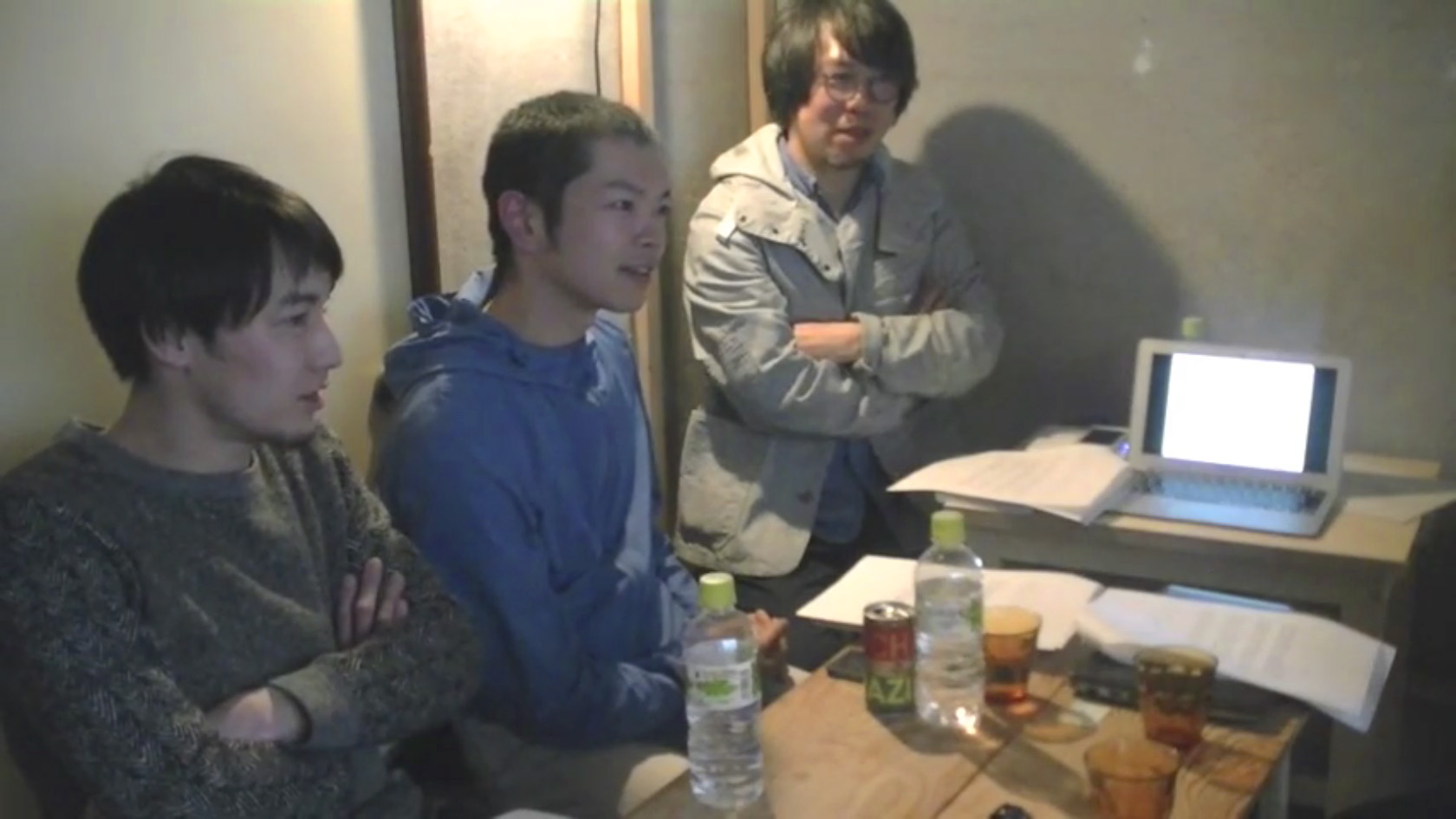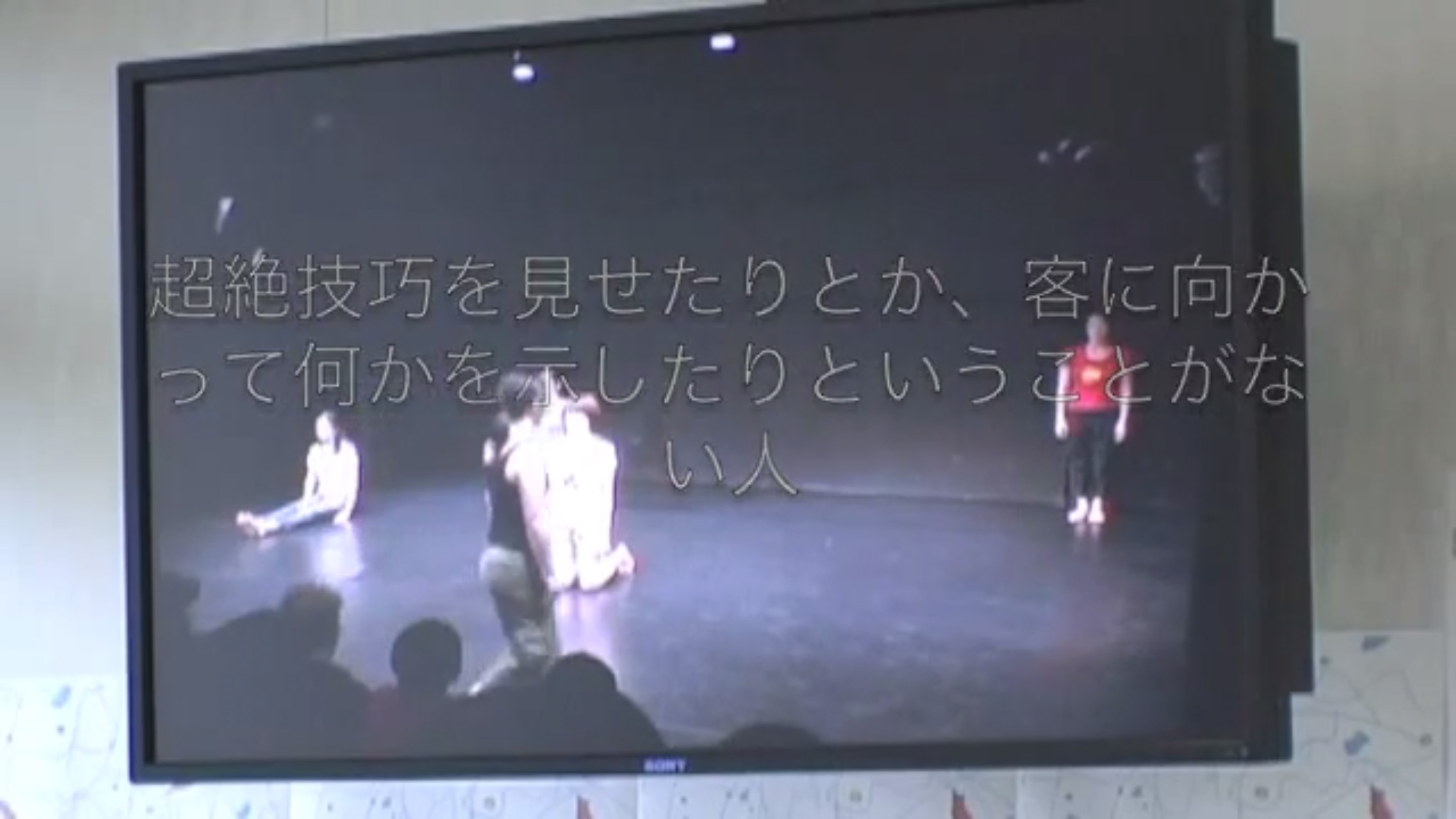2017/07/03
ここ数年の冨士山アネットの活動が、きわめてユニークで「コンセプチュアル」なものになっている。かつて冨士山アネットといえば、スタイリッシュなダンス×演劇でポピュラリティーを獲得したパフォーマンスユニットだった。これまでのテイストを愛好していたファンを置いてきぼりにするかのように、現在の長谷川寧は、あるひとつのテーマに執心し、かつてのポップさからは距離をとった舞台を作り続けている。長谷川がいま、とりつかれているのは「ダンサーとは一体何者なのか?」という問いだ。BONUSが「ワークショップ」を取り上げる際、まずは考えておきたいと思った問いも、まったく同じ問いだった。「ダンサーとは一体何者なのか?」という問いがクリアにならない限りは、ダンスの「ワークショップ」の受講者がどんな動機で、どんな欲望を抱えて受講するのかが理解できないだろうし、そうである内は、いくら高尚な「ワークショップ論」を立ち上げたとしても、それは独りよがりの空理空論に陥るほかないだろうから。だが、そもそも長谷川はなぜ「ダンサー(あるいはダンス)」へと問いを投げかけ、(いまだ日本のダンスシーンにおいて一般化しているとは言い難い)コンセプチュアルな作品を作るようになったのだろうか。インタビューは『ENIAC』への謎、のみならず長谷川寧という作家への謎へと突き進む。
取材日 2017/2/18
場所 森下スタジオ

『Attack on Dance』横浜公演/ photo by Hideki Namai
木村新作『ENIAC』★1を拝見しました。最近改めて冨士山アネットを見るようになり、昨年『DANCE HOLE』★2を観て『Attack On Dance』★3も観ました。長谷川寧さんが試みていらっしゃるコンセプチュアルな「ダンス」を問うダンス作品というポイントのユニークさもさることながら「ダンスとは何だ?」「ダンサーとは何者なのか?」と問う切実な気持ちが表出されているところに、惹きつけられています。『Attack On Dance』では「いくらお金を積まれれば、ダンスを辞めるか?」なんて問いを舞台上のダンサーたちに投げかけ、答えさせるなんて場面がありました。ユーモラスなフレーバーはかかっているけど、すごく切実な問い、ダンサーの実存というか、ダンサーがどんな欲望を抱きながら今の社会の中で生きているのかということに注目されていますよね。先日(2016/1/18)、長谷川さんにBONUSのイベントを見てもらいましたが、2016年度のBONUSは「テクノロジー×ダンス×X(社会的課題)」というテーマで進めてきました。ただ、ダンサーが踊れば良いってものじゃないだろう、例えば「テクノロジー」や「社会的課題」を連結されて初めてダンスは今日的な実質を帯びてくるようになるはずだ、というメッセージを込めていました。そしてBONUSは次の一年「ワークショップ」というテーマを展開していきます。その際に、そこに参加することになるだろうダンサーたちが、どういうダンスへの欲望を抱いているのか、ダンスを通して社会の中で何を実現したいと思っているのか、そうしたことを知りたいと思っていました。ならば、まずは「ダンス」や「ダンサー」にフォーカスしている長谷川さんに色々とお話を聞かせてもらうべきだろうと考えて、今回、インタビューをお願いした次第です。
- ★1
-
『ENIAC』(2017/2 @のげシャーレ)
http://artscape.jp/report/review/10132549_1735.html - ★2
-
『DANCE HOLE』(2015/2 @のげシャーレ)
http://artscape.jp/report/review/10120453_1735.html - ★3
-
『Attack On Dance』(2016/10 @KAAT神奈川芸術劇場大スタジオ)
http://artscape.jp/report/review/10128854_1735.html
長谷川ゼロ年代のいわゆる演劇で言うと、半径5メートルの世界しか描けないっていうことを言われてた時期があったと思うんですけど。そこから現在の演劇は割とダイレクトに社会の事象に向き合う様を描くようになっていったという印象があります。その事に対して、いわゆるダンスっていうのは身体を媒介として扱うが故の飛距離の伸ばしづらさを感じたりする時もあるんですよね。それが最近のダンスでは演劇作家が介入してダンスの試みをしたりとか、やっぱり飛距離の飛ばし方に対して色々アプローチしている。やっぱり社会的な課題ということに対して、何処迄ダンサーや作り手自身がシビアに、自覚的に捉えているかは気になります。僕なんかは逆に言うとダンスっていうのが作品づくりに於いて非常に便利なデバイスだと考えています。こう言うと言い方が雑かもしれないですけど、ダンスっていうものが答えのないものだから、そこに対してあやふやな形のものを求道している人たちっていうものっていうのは、一体何を求道しているんだろう?っていうことに興味があって。「ダンス」に対するそのあやふやなイメージっていうのは、もしかしたらダンスをやっていない観客それぞれの生活や仕事にも置き換えられるじゃないかと思って。最近はだからそういう風にその作品を観客が自身に置き換えて考えられるような活動をしているんですけど。BONUSをこの前見させてもらった時に、やっぱり社会的課題に対してどう取り組むかっていうことを、どこまでエンターテイメントに昇華するのかという事に挑戦されているところがあったりして、それに興味は持ちました。実際自分の作品でもダンサー自身はどこまで社会的な何か危機感や課題に対してリーチできているのか、という事を考えます。やっぱりどうしてもダンサーは踊りたいし、身体を使いたいという欲求があるから。じゃあそこに対して何をどう働きかけるというか、ダンスをしていない一般客だけでなく、当事者で有るダンサーにももちろん見てもらいたいと思って普段の作品を作っています。そこは自分にとっても課題だと思うし。

『Attack on Dance』サンパウロ公演/ photo by Rafael Salvador
木村長谷川さんも振付家でもあるし、ダンサーでもある。
長谷川ダンサーとは言っていないんですけどね。最早語弊が有り過ぎて。
木村でも、長谷川さんはダンサーの内に秘めている「踊りたい欲望」も、踊りの快楽も知っているのではと思うのですが、その上で、社会的課題に向き合うべきということに気づいているわけですよね。つまり自分の表現が「同世代の作家」と並べてどうなのかと考える視点を持っているわけです。当たり前と言えば当たり前の発想だけれど、必ずしも、ダンスの作家がそういう視点を持てずにいたりしますよね。
長谷川正直これくらい社会的に不安定だったりとか、色んな状況が浮かび上がって来てしまっている時代で、そういうポリティカルなことを扱いやすい時代になってしまった、とも思うんですよ、正直言って。勿論僕が方向転換したっていうのも、他の多くの作家と同様 、震災の影響とかもちろんあったし。じゃあそこで何をダンス公演見た後に感覚を残せるのかと考えた時に、切実さを求めたというのが一番大きくて。後は単純にカンパニーを運営するにあたってのマーケティングの部分もあったかと思います。
例えば、ある時にマシュー・ボーンを観に行ったんですよ。その時に全ての動作がすごく分かりやすくて。何で喋らないのかと思ったくらい直接的だったんですけど。それを客観的に観た時に、種類は違えど僕のやっていたダンス的演劇、というものの一つの商業的な到達点というのは、こういうことなのかと思ったんですね。でも、果たしてこういう表現を志向しているのか自分は?と考えた時に、いや違うなとも思ったんですよ。其処で何に対して誰に対して見せるのかとか、そういうことをすごい考えましたね。それが2013年のことです。そういう様々な考えることがありました。更にもう少し前の話になるのですけど、僕は元々影響を受けたアーティストとして、ラビア・ムルエという作家がいました。彼はレバノンでの自分が体験している内戦の話を作品にしている。ある公演では、来日する予定が内戦が始まってしまい実際に来れなくなってしまったから急遽スカイプ中継をして公演をやったということもあったそうです。そういう苛烈な現実にこの日本では何を持って立ち向かえるのかと思った時に、ドキュメンタリーとかに少し興味が湧いてきましたし、そこから色んな試行錯誤を経て今に至るんですけど。
木村平日昼間のワイドショー番組でもトランプの話ばっかりしているとか、いまや一番のエンターテイメントが政治であるような、そういう社会でもありますよね。「震災以後」「格差社会」「障害者との共生」など色んな社会的課題が転がっている、さて、そのなかで長谷川さんが冨士山アネットで扱おうと思ったのが「ダンス」であり「ダンサー」であるという点が興味深いです。案外そういうアプローチってあるようでないですよね。
長谷川それは結構理由はあって、元々僕は演劇の出だったので、学生演劇から入っていて。そこから学生演劇を経て、大学の内輪ノリの演劇サークルは嫌だなと思って、自分で劇団を作って4年間程活動していました。その後、自分がフィジカルシアターというか、例えば元々は惑星ピスタチオとか野田秀樹さんとかの身体性が強い作品に影響を受けていた事もあって、コンテンポラリーダンスに興味を持ち始めたりして。そこで自分もノンバーバルな表現、身体でどういう表現ができるんだろうと思ったときに、どんどん会話を減らしていって、最終的に台詞が全く無くなりました。その時の作品はまだマイムのパフォーマーがやった方が巧い、説明的な表現になってしまったんですよ。その時は俳優とか結構使ってたんですけど、俳優がダンサーやパフォーマーにどうしたら勝てる表現やメソッドを手に入れられるのかと突き詰めていきました。そこで、俳優が武器として持ち得る感情表現や生理的欲求を使うということが自分にとっての武器や方法論になるんじゃないか、と。変な話、一個の感情に対して振り切るという行為は俳優の方が実は得意だったりして。
木村「振り切る」って、何だろう。「(役の)感情に飛び込む」ってこと?
長谷川それもありますし、あるいは動きとしても、ダンサーはある意味受け身が得意であるというか。例えばこう腕を伸ばすという動きでも、それに対して踊りの方法論としてこう動かして、その後こう曲げていけば美しい、という仕草が身に付いているんですけれども、俳優たちは本当に力で行けるというか、欲求に対して直線的に行動できる、その魅力というのがあるなと思って。
木村あらかじめ自分の身体にインストールしてあるものに縛られないということかな。
長谷川ダンサーが共通言語として持ち得る動きのボキャブラリーとかそういう定型文の様なものではない俳優の動きに僕は興味が湧いて。例えば、水を飲むという行為をするとして、水を飲みたいという欲求、行動を細分化して見ていきます。するとコップを掴む、水を傾ける、コップを置くという動きに分かれているんですよね。で、それら一つ一つの仕草と欲求をどんどん大きくしていくことで、ある種の破壊的とも言える衝動を増幅して動き、振付に取入れていったんです。でもそれだけだとやっぱり動きが繋がらないんですよね。そこからいわゆるコンテンポラリーの要素を入れて、動きを構成していくようになっていったんです。そもそも、僕はダンサーではなくて、いわゆる恒常的な訓練を受けたことがないから、ずっとダンサーに対する憧れがあって、でもダンサーになれない自分は何をしたらダンサーに勝てる表現を手に入れられるんだろうって思って、そういうメソッドを考え始めて。そこから更に自分の表現は変わっていくんですけど。だからダンスっていうものに対して、漠然とした憧れはずーっとあって、そこが原動力になっているし、そこは一貫しているなと自分で思いますね。
木村面白いですね。長谷川さんにとってダンスの魅力ってどんなものなんですか。
長谷川魅力というのか分からないですけど、単純に身体として、例えば足が上がるとか身体が柔らかいとか、そういったものに対する漠然とした憧れだったと思うんです、最初は。でもそこから自分の中では、どんどんどんどん曲がっていったというか。ある時にふと、何でこの人は今足を上げているんだろう、ということを考え始めたんです。もちろんその人にとってはその動きは型なのかもしれない。バレエで言ったらその型に対して用語が決まっている訳だし。そういったものに対しての動きだと思うんですけど、そこに対してある時期から疑問を持ち始めました。そういう流れからか、最近調べていた事例として「舞踏」を面白いと思いました。というのも、今舞踏というジャンルは、誤解を恐れずに言えば超揺れている時期だなと思って。例えばテレビ業界と舞踏業界は同じくらいの長さの歴史だってことを調べててリハーサルで話題になったんですよ。テレビ業界って始まっておおよそ60年位らしいんですけど、そうするとまだ当時に教えられた人が残っている。というのがあって、大きな変革っていうのが生まれにくいんじゃないかって話をしてたんですね。それで今袋小路に入っている部分もあるのだろうし、実際ネットの表現に押されている部分もあります。そこと同じものが少なからず舞踏にもあるんじゃないだろうかって話になったんです。カウンターカルチャーとしてやっていったものがメインストリームというか、メインストリームというと語弊があるかもしれませんけど、ある種の型になってしまうというのは、これもしも土方さんが生きていたら現状をどう見たんでしょうね、っていう話をしていたりして。でもその現状とか、揺れている環境が良い意味で面白いなと思ったんです。僕ら世代からしたら土方巽というのは神様じゃないけど、最早そういうアイコンになっちゃってるじゃないですか。都市伝説というか。
木村『肉体の叛乱』のモノクロの8ミリ映像を見ると、本当に幽霊なのか実在する人物なのかと思うようなところがありますもんね。
長谷川木村さんって生で土方さんを観ている世代ですか?
木村僕は土方巽のことを批評文にして「美術手帖」の芸術評論募集(2003年)で賞をもらうんですけど、土方の踊りを肉眼視しないまま批評を書いた最初の世代だと思います。見たことないことを書くということと似ているかもしれませんが、『ENIAC』でも確か、会ってもない土方についてワークショップ中に外国の受講者に説明している自分のことをあげて、不思議な気持ちがするって石本さん言ってましたね。
長谷川舞踏というのは一人につき、一つの型という事を言われていて。だから舞踏譜という形は、正直、土方さん的には、どこまで本位だったのかと今では図りかねるところではありますけど。
木村「舞踏譜」って実際見るとアイディア・ノートというか、自分のイマジネーションを引き出すためのメモみたいなものだったりしますよね。もちろん解釈とかは多様で、和栗さんはかなり舞踏譜から土方の踊りのエッセンスを正確に受け取ろうとした。でも、土方巽のエッセンスは別のところにあると考え別のところから舞踏を引き出そうとした者もいたし。
長谷川和栗さんや彼と同世代の舞踏関係者の方々も『ENIAC』を面白がってくれたんですよね。やっぱり、 一線の方達は表現に対して寛容なのかなと思いました。和栗さんとかも僕が土方巽の役をやっているというのも、変な話色々思うところもあるとは思うけれども。それはそれとして観て下さった。僕は舞踏だけでなくダンスとか様々なジャンルが、どうやって生き延びるのかに興味がある。そういった意味で、すごく舞踏というのは面白いところにいるなと思いましたね。
木村和栗さんから受け取ったようなアイデアを元手にして、和栗さんが居ない形で石本さんは海外のワークショップに単独で行く事もあるわけですよね。でも同時に石本さんの踊りが海外でこれは舞踏ではない、と言われたと。じゃあ、私がやっていることは何なんだ、という問いが出てくる。そのことが「舞踏」の現在形を考える上でとても面白い。ただね。現代の目からすると舞踏というのは「加齢aging」に耐えうるダンスなんだということになるだけれど、もちろんそれは間違いではないんだけど、土方巽があれを始めた50年代終わりから60年代に、彼はまだ若手なんですよ。そう考えると、ある種あれは青春の踊りというか、20代、30代の踊り手が作ったものであって、そのことも同時に面白いなと思うんですよね。
長谷川ブラジルに公演で行った時も舞踏は人気で、実際に大野一雄さんとかはちょっと別格に有名でした。海外でダンスをやっている人の中では、ある種舞踏をファンタジーとかスピリチュアルなものとして捉えていらっしゃる方もいるそうで。
木村でも、ヒーリングとか、アートというのとは別に何かそういう健康のためにというかね、そういう舞踏の解釈も多いんでしょうね。

『Attack on Dance』北京公演/ photo by Killarb
長谷川だから僕が元々興味を覚えたのが、ダンスって基本的にはファンタジーの部分があると一般的にも思われている節があるんじゃないかと考えていて、そのファンタジーに現実を入れるとどう見えるんだろうというのが、作品作りの上で興味の湧いたところなんです。例えば[Attack On Dance]という作品が自分が「ダンス」というものを題材にしたシリーズの第一作なんですけど。DANCE TRUCK PROJECT★4に呼ばれた時に、時間がなくて稽古もできないという状況を逆手に取って、普段の自分の様に稽古をして作りこんで発表するというものではないもの、つまり敢えて自分の苦手なことをやってみようと思って、稽古5日間くらいある内の2回から3回以上来れればいいですよってことでダンサーを集めてやったのが、『Attack On Dance』という作品の原型だったんですね。単純にトラックの中にダンサーがぎっちり動けないくらい詰められてて、その制限された環境の中でダンサー達が動いたら面白いと思ったっていうのが、発端ではあったんですけど。普段は自分の中で作品の評価っていうのは、幕が開くまで分からないんですけど、今回は発表する前に珍しく、これはいい作品になりそうだなっていうのを感じて。そこから大分自分の中で作風は変わって行きましたね。
- ★4
- 「トラックの荷台スペースを移動可能な特設ステージとして使用し、周囲の景観を取り込だサイトスペシフィックなプロジェクト」(DANCE TRUCK PROJECTサイトより)
コンセプチュアルな構成の謎
木村「色んな身体性のダンサーがぎちぎちにトラックという舞台に詰められている」というのが面白いというのは、まだダンス的な発想ですよね。でも、彼らがどんな人間で日々どんなことを想って、ダンスと関わっているのかをリサーチして、その内容を舞台にしようと考えるのは、単なるダンスについての感性的な発想を越えたコンセプチュアルな発想ですよ。長谷川さんは「テアタータンツ」って言葉で自分のスタイルを表現しますよね。それでいうと「シアター」の発想というか。ダンスは運動です。流れていく川とするならば、「シアター」っていうのは、川を一瞬切り取るフレームみたいなものですよね、「お弁当箱」とすれば、箱の中に運動するものを詰めちゃう。詰めた時にどんなものが現れるかというかね。その詰め方がリサーチだったり、アンケートだったり、長谷川さんが狂言回しみたいな形で舞台の中に出てくるということだったりすると思うんだけど。ああいう構成ってどうやって生まれたんですか?
長谷川僕はそういう影響を受けた中では、ジェローム・ベルが大きかったですね。そこに対してこういうやり方があるんだ、と思って。
木村とくにどの作品ですか?
長谷川ジェローム・ベルでいうと、自分が出演させて頂いた『ショー・マスト・ゴー・オン』もそうだったし、彼以外の作品ですと、リミニ・プロトコルの作品群とか、ああいうもの。そこから影響を受けている部分も多分にあります。そういった形って、やっぱり日本でもまだまだ少ないけれど、もうちょっと多様化してもいいんじゃないかと思います。『Attack On Dance』はある意味ダイバーシティ、多様性というものをどう扱うか、どう見せるかということをやりたかったというのはありましたね。
木村『Attack On Dance』見て、ようやく日本のダンスが「コンテンポラリー(同時代の表現)」になったという気がしました。ダンスをダンスのままで出さず、メタレヴェルの「シアター」の発想で舞台に上げる。ダンスについてのダンスというか。


『ENIAC』/ Photo by Hideki Namai
長谷川例えば今回の『ENIAC』に関して言えば、それでも相当演劇寄りだったという気はします。やっぱりお客さん、例えば全く一般の仕事をしている自分の友人が観に来る、といった時に、研究発表をしてもしょうがないし、そこに対して観客個人のそれぞれのテーマを扱っているように観る事が出来るもの。例えば『ENIAC』で言ったら、一般的な仕事をしている方々や、例えば転職を考えている方とかにも響く作品になるといいなと思って。
木村長谷川さんのそういう発想ってそれもあんまりないなと思うんですよね。エンターテイメント志向と言いますか、お客さんのことを考えている。誰が観るのかということを考えてますよね。石本華江さんという一人の存在の幼少期から高校時代の現代舞踊・モダンダンス、大学ではコンテンポラリーダンス、20代後半で舞踏に出会う、といったダンスの個人史をかなり丁寧に調べて、お母さんとの関係性も出てきたり、実際に長谷川さんも彼女の実家に行ったりして、見せる。このドキュメントの丁寧さが印象的でした。さっきの「シアター」の話にも繋がるんだけど、BONUSの場合、僕がアカデミシャンだからかもしれないけど、「開い」ちゃうんですよ。パフォーマンスの直後に演者にインタビューしたり。舞台に込められたものを「アイディア」という形に変換して観客と共有しようとしてしまう。長谷川さんの作品はもう一回捻りが効いていて、それを上演作品(シアター)の形にして「閉じ」て封をして観客に観てもらおうとする。楽しんでもらおうとする。長谷川さんの観客を楽しませようとする意志というものについて、是非伺いたいなと思っていました。
長谷川それはたぶんそれが元々は苦手だったからです。というのは、お客さんに対してかつての僕の振付は、土方巽の舞踏譜に興味を持ったのも同じ理由なのですが、テキスト、戯曲を書いてそれを動きにしてきました。で、読み合わせをして、セリフを覚えてもらって、立ち稽古をして、最終的には台詞を取払うってことをしていたんですけど。ある意味僕はある時期はお客さんがどう捉えてもいいと、そう思ったんですね。物語をどう曲げて解釈してもらってもいいというか。だけどそこに対して、震災時に起きた議論ですけども、フィクションを超えた圧倒的な現実に対して今公演をしている場合なのかとか、こんな問題を孕んだ時期がありました。そこで自分ももれなく今お客さんに見せるべきものは何だろうと考えたし、月並みかもしれないですがそういう未曾有の事態がまるで当たり前の顔をして日常に入り込んで来た事で色々変わっていったのは事実ですね。それで自分の苦手な事ということでも食わず嫌いにならず敢えてやってみることで、表現に対して貪欲になりました。もう表現としてよければ台詞も話すし狂言回しでも何でもやりますよ、と。ある種エンターテインメントというものは自分にとってのチャレンジなんですけど、そういった挑戦をしてみようと思った背景にはそんな事がありました。自分にとって苦手な事をやることで新たな道が開けたという意識はあります。アンチ自分というか。
木村ダンスについて自分は憧れはあるけど、望むような踊りができたわけではないというお話もありましたが、上演を構築する手腕というのは、むしろそれが苦手だからだという……
長谷川ダンスっていう表現として掴みどころの無いものを扱いながらも、お客さんが直接的なリアクション、例えば笑っている状況を作り出す、という事に興味を持ったんですよね。勿論笑いというのは感情としての一例ですが。例えばダンスの中で少しコミカルな動きをしてみるとか。そういうのではなくて、ちゃんと意味があって笑わせる。ちょっとした仕草が面白いんじゃなくて。ということってダンスにとっては挑戦だなと思った。
木村分かりやすい笑えるポイント、リズムとか変な顔をするとか動きによくあるコミカルさを足すとか、でもそれをやって分かり合ったところで、なんか虚しい、ということがありますよね。ダンスそのもののポテンシャルにもっと期待して、それを引き出そうとする真摯さを求めてしまう。ところで、観客とコミュニケーションを取り、ダンスについての理解を深めてもらおうとする時に、長谷川さんが出て、石本さんと対話をしていく。演劇的な対話をダンスに持ち込むというのは結構冒険的なところもありますよね。でも、「コンテンポラリー(同時代)」なダンスの上演であろうとする際には、必要な要素のような気がするんですよ。
長谷川でもそれこそジェローム・ベルや様々なアーティストも対話をアプローチとした作品は結構やっていますよね。だからまだ僕の中では過程だなと思ってて。じゃあ自分は一体今後どういうまな板を出して作品を料理出来るのか、というのは考えますよね。
木村さっきダンスを「川」で例えましたけど、一旦「川」が堰き止められると、川は川ではなくなってしまう、一種のサンプルにはなりうるかもしれないけれど。面白い趣向だし、それで観察できることもあるけれど、と同時に、例えば、石本さん自身のダンスはやっぱり石本さん自身の公演を観て初めて分かる部分があるのだろうとも思ってしまうんです。混ぜっ返してしまうけれど、石本さんは『ENIAC』の方法に拒否反応を示すということはなかったんですか?
長谷川基本的には僕が観て作中にも取上げた『Hello, Mr. Hijikata』★5という作品とかも、彼女はスピーチする。結構スピーチしながら途中で踊りも入ります。だから喋るという行為に関しては、もちろん大丈夫だったんですけど。ただある種演劇的な部分で、どうしても追って行かなければならない部分、そういうところに関しては、私は俳優じゃないから難しいな、ということをずっと言っていましたけど。
- ★5
- 石本華江『Hello, Mr. Hijikata』
木村例えば、(一つのダンスを部分的に切り取って)抜粋で踊るじゃないですか、ああいうやり方、石本さん本人はどうだったんですか?
長谷川そこに関しても全然大丈夫でした。もちろん抜粋で踊るというのは、一本観た方がいいのは分かっているし、ショーケースじゃないからというのは本人自身も分かっています。
木村企画意図を理解して、踊ってくれたということですね。
長谷川そうですね。だから僕、ショーケース型の上演って自分も主催した事も出させて頂いた経験も経て、結構難しいなと思う時があります。ショーケースの中の10分から30分の品は日本のダンサーはものすごい作りっぱなしというか。あれが残念に思う時があって。作りっぱなしというのは、言う程発表出来る場所や機会が少ない、という意味です。コンペとか発表した10分20分の作品というのが、じゃあその後どうなるんだろうと思った時に、結構使い捨てということが現象として起こっているなと思うところがあって。
木村60分を超えるしっかりしたヴォリュームの作品を作る前に、ショーケースのための作品を作るステップがあった方がよいと考えがちだけど、しかし、実はそうではない。
長谷川それがどういう事かというと、結局は小作品なりの限られた予算内で作るということ。そうなると、彼ら彼女らは潤沢な環境の無いまま、作品を作らなくてはならない。それが続いて、結局一晩ものの耐えうる作品を作る訓練をする環境に自分の身を置けないまま、というのは、非常に窮屈な状況だと思うんです。だから日本の若手のカンパニーが少ないのもそういう理由なのではないかなと思います。で、出来ちゃうんですよね、小作品だと少ない人数で。予算的にも大きなリスクを背負う事なく。それが増えるものだから、大人数を扱うとか、カンパニーを背負える人がいなくなるというのは、僕は非常に課題だなと思っていて。だからカンパニーを持って作品を作っていきたいっていう子がいると、応援したいなと思います。僕は今外部で振り付けしたりする事もありますけど、大人数を扱う時もしばしばあります。そういった時にダンサーの人にアシスタントをお願いする際には、なるだけ自分が作品を作りたい人を連れて行きたいなというのはありますよね。
木村僕がコンテンポラリーダンスに執心するようになったのは、1998年くらいです。その辺りから4,5年くらいの間というのは今振り返るととてもよい環境ができていたような気がしています。STスポットに「ラボ20」★6という20分の作品を発表する新人公演のシリーズがあって、新人の才能をそこで発掘できた。そこで評判を得た作家には、セゾンが主催していたシリーズ「ネクスト・ネクスト」★7という30分くらいだったか20分より長い尺の作品を作るチャンスが、次のステップとしてあった。そこでさらに話題になると今度はトヨタ・コレオグラフィーアワードとか各自の本公演とか、60分だったり90分だったりの作品を作るチャンスが待っている。こうしたステップアップの流れが環境としてあったんです。現在はこうした環境がなくなってしまった。
- ★6
-
ラボ20: STスポットが1998年ごろから行っていたシリーズ。手塚夏子、捩子ぴじん、東野祥子などコンテンポラリーダンスの作家を輩出する場となっていた。
http://stspot.jp/finished/stlab20-20-restart.html - ★7
-
ネクスト・ネクスト: セゾン文化財団とパークタワーアートプログラムが共催で行われたダンス公演。「パークタワー・ネクストダンスフェスティバル」のプレイベントとして行われていた。
http://mneko.la.coocan.jp/play/SA/20041218m.htm
http://www.saison.or.jp/viewpoint/pdf/01-02/17-4.htm
長谷川当時って、パークタワーのダンスフェスティバルがあったりだとか、色んなものがあったんですけど。僕の中ではJCDNの「踊りに行くぜ!!」が当時、全国各地にスター選手が派遣されていく、みたいな活動をしていて、あの各地に広がっていく活動は波及活動としても素晴らしいと感じていました。それを経て、今度は「吾妻橋ダンスクロッシング」を知り、良い意味でもっとよく分からない人たちがいっぱい出てきて、スターになって、という状況が面白いなと思ってて。でも吾妻橋もトヨタ・コレオグラフィーアワードも終わり、そこからスター不在のイメージになったんですよね。僕はそういうスターたちがもっと出て来たり、出て来れる様な環境がもっと有った方が、シーンとしては豊かなんじゃないかとは思います。
木村若いダンス作家が憧れたり、目標にしたりするような、自分を映すような先輩の存在が見えにくくなっていますよね。ダンスの分野が弱体化している大きな原因と考えます。
長谷川可視化できるものというのが、もうちょっとあった方がいいと思うし。自分がやっている活動というのも、最近はダンスを可視化するということをすごく意識してやっていますよね。踊りって本当に一般的には分からないものだと思うんですよ。それをじゃあどうやって観るんだろうってなった時に、そこの媒介になれたらとすごく思うし。
木村長谷川さんは、エンターテイメントへの意識あるいは観客の存在への意識もありつつ、ちゃんとダンスの根っこみたいな部分も意識されていて、そうじゃなきゃ『ENIAC』みたいな作品は出てこないと思うんだけど。
長谷川たぶん観客の、受け取り手側の気持ちというものを今まではどこかでないがしろにして来てしまった部分は有るんじゃないかと思います。踊ってあとはそれぞれが勝手に受け取ってねということをやってきたからこそ、今は受け取り手側がどう観るとか、どう還元できるのかと考える方が双方にとっても有機的だなと感じるようになったというか。受け取り手にとって琴線に触れる何かに表現で関われる事が出来れば、結果それがもたらすリアクションが自分にも返ってくる。作品を作るきっかけも、自分が何かからもたらされる事が多い。例えば『ENIAC』ってタイトルも、世界最初のコンピューターの名前から取ってるんですけど。こうやってふとした所から自分が気になった事柄から作品を広げていくタイプです。そうやって気になった事柄はなるべくストックしておきます。これが作品になるかどうか分からないですけど、最近気になったのがネットで見てたニュースにオカルト番組が流行らなくなったと、その理由って何だろうという記事があって。それは心霊写真とかが、SNSやPCの技術が発達したことによって誰もがアクセスをし、誰もが真偽を確かめられるようになってしまったからだ、と。だから心霊写真というものが圧倒的に減った、というのがあって、すごい納得したんですよね。多分そういう事なんですよ。通常ある概念に対して疑いを持って、拡張する事というか。それが僕の作品の根源だと思います。

『ENIAC』/ Photo by Hideki Namai
木村さっきの長谷川さんの過去の作品について観客は自由に受け取ってくれたらいいということと少し繋がるんだけど、ダンスの公演を観てると時々何を伝えたいのか分からない、曖昧模糊としている分、色んな意味が受け取れそうな気もするんだけれど、でも掴まえようとすると手に何も残っていない、そういうことがしばしば起こります。「ファクト」を探せないんですね。じゃあ勝手に「私にはこういうものだ!」と思い込み、それで良ければ何となくそれで回っていくのかもしれないけれど、今の心霊写真の話みたいに、「本当は何なの?」って言い始めると、ぼんやりとした表現は淘汰されざるを得なくなる。
長谷川それってすごく演劇もダンスでもそうなんですけど、僕はある種ブランド化なのかなと思っていて。例えば作家の誰々の作品、というだけで皆が神格化している時ってあるじゃないですか。あの人の作品はいつもハズレ無し、みたいな。どこかにみんなちょっとブランド志向があると思うんです。それ自体は全然悪い事では無いし、カンパニーや作家としてブランドを作れているというのはある種戦略として成功している訳じゃないですか。只たまにSNSに並んだ所謂ブランドを賛美した感想を覗きながら、こんな賛が並ぶ事って本当?と思う時がある。其処に否を投じる事に何か踏み絵の様な緊張を強いる空気というか。
木村自らの感性で面白いと感じ、ファンになるというよりは、「これが今ウケてる」という情報に追従してしまう。
長谷川それがステータスになっているというか。でも先程も言った様に僕は悪しとも思ってなくて。例えば僕は別に自分が好きなタイプの踊りとかではないんですけど、全く違和感を感じずに観れるものもあります。それは、この人たちはこれを踊るしかないんだなというある種の切実さを持った踊りです。そういったものが僕はすごく好きで。凄く根源的な、祈りにも近い様な宗教的な感覚になるものもありますよね。
木村それは仕掛けとしてそういう観客への狙いが込められてる?それがややカルト的であったり……
長谷川それもある種良い意味でブランドだと思うんですよ。どれだけ長かろうとそれを観ていられるとか観るという。ある種ダンスの本質的な部分というか、そこには元々そういう儀式的な部分であったり、祝祭的なものがありますよね。確かに自分は儀式的なものとしてダンスを扱っているわけではないですけど、今でも儀式としてダンスがちゃんと成立しているという視点も尊重したいと思っています。
木村必然というか、成るべくして成っている「動き」があるとして、でも、そういうものが掴めない、よく分からないものとしてダンスが社会に受け止められているというところは否めない部分でもあり。そういうダンスというものを長谷川さんは「シアター」化して見せ物、観れるものにしているという気がしますね。
長谷川『ENIAC』の前半で僕が話していた、「『ダンスって何だろう?』という作品をいつまでやれるんだろう?」っていう事は、常に自分は思っている。今はよその現場で、振り付けをしたりだとか、そういったところで自分の中で表現欲求としてのバランスは取れている。例えば画を作りたい、という欲求は外部の現場で満たされている所があって、だから自分の所ではこういうコンセプチュアルな表現活動ができるっていうのはあるんですけど。それがひと段落したら自分はどこに向かうんだろうというのは見えないけれど、それも含めて自分がどうやって道をドライブしていくかってことはすごく面白い事です。勿論どうしようかなっていつも思いますけどね。
木村オペラの仕事とか色々な振り付けの仕事をされている長谷川さんの活動は、若い子からすれば順風満帆に見えるかも。しかも、それに飽き足らずコンセプチュアルな作品にもトライしていて、バランスが取れているし。でもこのバランスが取れているかに見える長谷川さんは、逆に言えば、バランスを取らないといられないくらい切迫したものを感じている気がするんです。
長谷川それはもしかしたら『ENIAC』でも取り上げた、いつまで続けられるかという辞め時の話にも続いていく話かもしれません。本当に今の興味として、例えば野菜というものに興味を持ったとして、どうやってもステージ化できない、となる可能性もあるかもしれないじゃないですか。急に畑を耕し始めるかもしれない。つまりこういうコンセプチュアルな活動を続ければ続ける程興味が拓けて来てしまい、結果表現形態として舞台で無くなる可能性だってある。よく一生舞台は辞められない、という方もいらっしゃいますが、逆に自分達はいつでも辞められるんだ、という意識で舞台をやって行く方が覚悟がいる。 だからこそ逆に言えばカンパニーとしてコンスタントに活動するということが、自分の矜持でもあるというか。だから、外部で振付もやりつつ自分のカンパニーの公演もコンスタントにやってらっしゃる方達がいるじゃないですか。やっぱりそれって素敵だなと思います。カンパニーで活動する事自体が名刺代わりになっている。最近の自分のカンパニーの作品はコンセプチュアルだから外部での汎用性が低いんで、正直名刺にはなりにくいんですけどね。
木村ダンスを辞めるかもしれない、ならば、それはいつか。それは、一般化できる、まっとうな人間としての悩みでもある訳じゃないですか。この悩みはダンスに限らず、広く様々な場で人々が経験していることですよね、そこにアクセスしていることが面白いんだな。
長谷川30代の俳優とかダンサーを見ていると、すごく興味深いのはそういうところで。いつまでやれるんだろうとか言うけど、正直やり続ける事は出来てしまう。けれど人生の経験値としては上がって行くので、金銭的であったり環境としても豊かな生活がある事は知っている、知ってしまう。多くの人にとってそういう生活を自分がしたくない、というのは嘘だと思うんですね。現実的な生活と表現欲求が起こす摩擦やジレンマとか、そういったものに対して興味はありますよね。其処に対して人がどういう風に悩んでいるのかとか、やっぱりそこが現実的だし、興味深いですよね。

『ENIAC』/ Photo by Hideki Namai
長谷川から見た「ダンサー」
木村話をちょっと変えますね。色んなダンサーと接している長谷川さんの目から見て、ダンサーってどういう人ですか?何で踊ってるんですか、何で踊りたいんだろ?
長谷川何で踊りたいのかってことに対して、それこそ考え始めると踊れなくなっていく人も多いんですけど。
木村じゃあ「ともかく夢中になっている状態」というのも大事なんだ。
長谷川そういうある種のフィーバー状態というか、やっぱりその魔法っていうのが年齢を経るにつれて、薄々ちょっと違うんだろうなと思う時もあると思うんです。もちろん人に依りますけど。いつまでこういう風に、本当にあなたは全く芽が出なくて、全く誰にも理解されずに、本当に踊り続けられますか、っていうことももちろんそうだし。そういったことに対する色んな答えを持っていることがダンサーであると思うし。一般的にダンサーは身体がとにかく基盤だから、 年齢を経て、これからが良い踊りになるだとかますますダンスが練られていく、という考え方って、ある種残酷な言葉だと思うんですよ。そういう優しさって。だって本当に自分が踊りたい踊りに若さが必須な人っていうのは絶対にいる訳ですから、そういう人たちにとってそういった言葉や考え方は悪い言い方をすると延命措置に聞こえてしまう。実際、多くの一流カンパニーのレパートリー作品で踊っているダンサーは平気で20代とかじゃないですか。そういった事実と向き合った時に、そことの付き合い方によって、非常に個人個人の答えが見えて来るし、そこの揺らぎを見せてくれるのもダンサーだと思っていて。
木村もちろん、若くてエリート的な身体が、バキバキにトレーニングした成果を観客の目の前で披露してくれて、それが圧倒的な感動を呼ぶというのが、一つの絶対的な正解だとして。でもそれができるのはごくわずかなエリートに過ぎず…… 99%のそれ以外のダンサーは……
長谷川プロ野球に近いですね。1球団のナイン×12球団。主に活躍出来るのはその108人。たった108人なんですよね、結局。それもごく短い期間で、更に言えばそれは頂点の一角に過ぎない。其処からベンチを始め、2軍3軍とピラミッド状になっていく訳じゃないですか。そこの人たちの暮らしぶりっていうのは、そういう現実はダンスにも往々にして起きている事だと思います。
木村『Attack On Dance』の成果は「どんなダンサーも面白い」、その視点をダンス公演あるいはダンスの世界に置いてくれたことにあります。ダンスというかダンサーに注目したわけですよね。長谷川さんの言葉で言うと、ダンサーには一種の揺らぎみたいな葛藤があると。葛藤は単に心の葛藤ではなくて、身体の表面に露出してくるような葛藤があると。それが滋味深い。
長谷川『Attack On Dance』に関しては何が面白いかと言えば、結局すごく本人たちと話をして行くと基本的には慣れてしまうから、舞台上で聞く質問とかに関してより各自が作るソロダンスに対してまるで僕が各人のドラマトゥルクの様に向き合う、というのが主なリハーサルの進め方なんですね。まず最初に「10年後も踊れるダンスを作ってください」と提示する。何故10年間かっていうのは、10年も踊る事に耐え得る作品というのは、自分に核がないと踊れるダンスじゃないんですよ。何でそのテーマを選んでいるのっていう所から内面迄入って行って延々と押し問答して、ということで作っているんですね。
木村それが主なリハーサルの時間な訳ですね。
長谷川そうです。そこに対して片や観客が観る時には、10年後の云々とかは勿論知らない。様々な質問やプライベートを晒け出して行ったダンサーが、結局最後7分間本業の踊りで一体どんなダンスを見せてくれるんだっていうことで、観客側としてはずっと求めていたダンスをようやく最後に観る事が出来るじゃないですか。観客はそれまでの過程で各人のプロフィールを全部知って、自分の好みのダンサーが生まれていますよね。だから悪く言えば非常に選り好みした目線でダンサーを選ぶし観ている。所謂ダンスが持つ神秘性というか、そういったものを全部剥ぎ取って観た時に、意外と自分が気に入っていた人が、自分の想像していたダンスをしてくれなかったりとか、そこで自分にも気づかされるというか。自分はあの人をこういう目線で見てたなとか。そういう一喜一憂が面白いなと思って。
木村見ていて『Attack On Dance』の出演者たちは怒らないんだろうか、と思ったんです。最後に踊る場面があるにせよ、ほとんど踊らない。踊らせてくれない。質問に答えるとか、ダンサーがダンス以外のことをしている。これはかなりストレスがあるだろうと思っていました。そしたらリハーサルの時には長谷川さんが付きっきりで彼らの10年後も踊れるダンスを一緒に作っていた、と。そうかあ。その時間はたぶん彼らにとってとても有意義な、公演に参加することの意義という点でかなり重要な時間だったでしょうね。
長谷川面談みたいなことをずっとする。それは上演した各地で同じですね。まずコンセプトを理解してもらわないと意味もないし、最後の場面迄は踊らない理由と言うのもそこに、最後に集約しているからということを伝えないとですよね。
木村ある種のダンサーへの平たく言うとサービス。あるいは、丁寧に言うとダンサーというものの何か苦悩みたいなものを長谷川さんが受け止めていく時間のような気もするな。
長谷川だから辛いですよ。ずっと自分にそういうダンサーが持つ欲求、それは負の部分等もままあるので、そういった黒い部分は堆積して行きます。家族間の問題とか、生死に関わる事とか迄。でもそこを聞き出すまでに時間もかかるし、そういうものの吐露が始まった時に本人たちの踊りも変わって来るし。やはりそこが面白いなと思うので、核を知れるまでは掘り下げて行きますね。
木村単にコンセプチュアルな作家だったら、リサーチをして最後の7分は自由に踊ってくださいと言うだけで、上演しちゃうかもしれない。そうすると、結果的に僕が想像するに、ダンサーはストレスが溜まるのではないかと思うんです。踊ったけど俺どうだったんだろうって。すごく重要なことのような気がします。というのは、ダンサーってプロ野球選手の例えかもしれませんけど、一握り以外の人たちの人生が詰まった現場ですよね、ダンスの世界は。でもこれはちゃんと社会の力のはずで、この人たちが元気よく輝けるというか、何か才能を出してもらう、力を出してもらうには何をどうしたらいいんだろうと。その人の独りよがりみたいなことで終わっちゃうのでは寂しいですよね。苦悩みたいなものを吐き出す場でもいいんですけど、ちゃんとダンスが機能している状態っていうのが社会の中でどういう風に生むことができるのだろうと考えるんですけど。
長谷川何をダンサーは持っているんだろうっていうのは、もちろん人それぞれだし。こういうコンセプトでやっているから、結果残る人は何処か不可思議な人たちが多いですよ。応募して来る人は、何かしら違うことをやりたいんだろうなっていうことはあるだろうし。とりあえず募集があったから応募しちゃうっていう人もいるだろうし。そもそもダンサーっていうのは、表現出来る場が限られているんだな、とは思います。
木村場が少ないという社会的状況もありますよね。あとそもそも自己表現したいという欲求もすごくある。それがダンスじゃなくてもひょっとしたらいいかもしれないけど、ダンスってことにとりあえずこだわって。
長谷川『Attack On Dance』の場合は最後にできる個人が作る作品は著作権フリーであなたたちがどこでも上演していいですとしています。それは逆に言うと今後も踊り続けられる強度のあるものを作ってほしいと言う意味でも有るんですけど。
木村繰り返しになっちゃうけど、要はそれは長谷川さんというちゃんと力のある作家に付き添ってもらって自分のレパートリーを1個作るみたいな過程な訳じゃないですか。
長谷川確かにある意味ワークショップ的な側面も多分に有りますよね。
木村そう、むしろワークショップでの出来事のように聞こえるわけです。得てしてワークショップって誰か振付家のアイデアを教わる場になる時もあって、それをいわゆるワークショップって言わなくてもいいような気もするんだけど。そういうものよりずっと「ワークショップ」になっている。長谷川さんのリハーサルはむしろその作家の力を一緒に引き出してあげるみたいな、むしろワークショップ的だと聞きながら思いましたね。
長谷川BONUS(2017/1/18のイベント)を見た時にもこれはどういう形態なんだろということはすごく思いましたね。ワークショップなのか、何なのかなと思いましたし。僕は印象的だったのは発表の中でパフォーマンスがあって、作品の性質上、その振付家の方がアフタートークの様な形では解説はしたくないという趣旨で。代わりに受付に紙を置いておくので気になった方は読んで下さいと伝えていた事でした。喋らない、けれど紙を置きます、というのは、このBONUSという場に置いてどういう意味を持つんだろう、と感じて。僕はそういう作家の趣旨であれば紙すら置かなくても良いんじゃないかと思ったんです。そう感じた事も含めてワークショップなのかパフォーマンスなのかっていう線引きはともあれ、BONUSは僕は開いている感じがするのは良い事だなと思ったし、ああいう研究発表の場でもあるんですけど、外枠としてポップだなと思いました。そういったフォーマットは凄く興味深かったです。研究の外にいる感じもするというか。ただアフタートークでも仰っていたように、木村さんの立ち位置は難しいですよね。オーガナイズしないといけないけど、しすぎても何かというか。
木村『ENIAC』を拝見すると長谷川さんがされていた仕事というのと、自分があの場でやっていたことが重なる部分があって。でも長谷川さんのウェルメイドなちゃんとセリフを用意して、場を作っていくことが僕はやりたいのかというと、ここら辺がどっちが良い悪いということじゃないですけど。あるいは、長谷川さんのはそういう風にして作品にしようとしている訳だから全く問題ないとは思うんだけど。じゃあ僕は作品にしたいのか…僕は社会が作りたいと思うんですよね、ダンスを生み出す場で。あえて言えば長谷川さんが紙を置いちゃだめだと思うっていうのが、僕の中では一種そういう風にダンスを巡って人々が考えて、俺だったら置かないと思う、それは一種のクリエイションの何か、目というか、そういう気もするので、そういう事がしたいんだなって思う。

『ENIAC』/ Photo by Hideki Namai
長谷川どういう形でやればいいのかということを、別に答えを出さなくてもいいし。例えば『ENIAC』で言えば、自分は彼女に一方的に聞くMCにならないようにしよう、対等でいようと考えました。つまり僕がヒール(役)になることは簡単なんですよね。舞踏に対しておかしいだろとか言う事はできる。だけど、それを言っても誰も幸せになれないなと思って。誰も幸せになれないなというのは、作品として。じゃあ僕は何をさらけ出すんだろうと思った時に、最初は「石本さんはいつ辞めるの」だったんだけど、実はそれは映し鏡で「僕がいつ辞めるか」という事を考えているからなんだろうな、ということに気づかされた、ということですよね。勿論これは単純にもうやりたくない、とかそういった簡単な構造では有りません。其処には肯定も否定も併せ持ったものがある。結局そこを出していったというか。
木村あの作品の作家性みたいなところがあるとしたら、何かそこのような気がする。長谷川さんが自分いつ辞めるんだろうって、セリフとして言っているだろうけどかなり切実のような気もする。さらけ出している気がしたのは、結構大事な要素だったりして、そういうところまで出てこないと、やっぱり作品としては、観客にとってインパクトが不十分なものになってしまうかもしれなくて。そこはすごくいいなと思います。
長谷川すごい面白かったですよ。久しぶりに観に来てくれた批評家の方も、作中で扱われる石本さんの学生時代の作品を実際に観てたりしていて当時の失敗を経て、今回観て楽しんで頂いて、石本さんとは祝リベンジ。なんて話をしていました。
木村面白いな、舞踏がらみだと舞踏のお客さんたちが、ぞろぞろ観に来て長谷川さんを取り巻いたわけですね。あえて問題だなと思うこと言えば、タコツボ的に見えるところです。舞踏の公演には舞踏がらみの客が来て、コンテポラリーだというとその趣向の人が集まる。でも、長谷川さんの公演がまさにそうだと思うけれど、タンツテアターとか言うと「タンツ(ダンス)」と「テアター(演劇)」の2つが連携している訳じゃないですか。2つの可能性というか、そうすると跨らざるを得ないわけで。長谷川さんのあの作品を観て「俺だったらこういうことしたい」って、横断的なことがあちこちで始まると良いなってすごい思うんですよ。
長谷川僕はあの作品を観て貰った時に、観客には一般的に舞踏に思われがちな、何かわからぬ怖そうなものであるという思い込みを外して、少しでも興味が湧いてくれればいいなと思って。もっと評価すべき格好良い側面というか、そういった部分にフォーカスを当てたいなと思っていて。例えば表面的な部分だけでも土方巽とかの昔の写真とかを見ると、本当に只々美男子だったりもするんです。でもそういうのって知られてなくて、一般に紹介される時はそういったものではない、おどろおどろしい映像で出てたりとか、そういう所ばかりが非常にフォーカスされちゃっているのがもったいないなと思って。それくらいアクセスし辛い状況になってしまっているんだなと思って。最近舞踏とか観に行ってます?
木村でもね、いくつか流派があるので観るものと観ないものとがあるんだけど、
長谷川最近で若手で注目されて来ている舞踏家ってどんな方がいらっしゃるんですか?
「舞踏」と「コンテンポラリーダンス」をめぐって
木村若手っていうと…… 僕は駱駝艦周辺を比較的観ているんですよ。捩子ぴじんや向雲太郎など、優れた表現者が多数輩出されている舞踏の学校のようにイメージしています。今回「ワークショップ」を掘り下げるに当たって、麿さんに若者を育成していく場をどうやって作っているのか聞きたいと思ってます。ところで、ちょっと話を切り替えると、僕は舞踏を紹介したいっていう長谷川さんの気持ちが分かると同時に、長谷川さんのあの作り方に感染して欲しいと思う。若い作家たちが「そっか、ダンスを見せるって踊るだけじゃない。踊ることの枠を作ることで、踊りっていうものを見せる見せ方を色んな形に出来るんじゃないか」って。「もうすでにやっているよ、当たり前になってる日本以外の世界では」とも言えるけれど、とはいえ、まだまだそういう風なアイディアが多数試されているという状況でもないですよね。
長谷川おこがましいかもしれないけれど、それが舞踏の人たちに何か起こることがあるかもしれないと期待していて。例えば若手で注目されている舞踏家を周囲に聞いて調べてみても、でもやっぱりフォーマットは舞踏っぽい舞踏なんですよね。まあそうでない人はコンテンポラリーとかに移行していったりもするんでしょうけど。それがもうちょっと舞踏をすごいラフに扱うと言うと言い方が変ですけど、そういう人がもっと出てくると面白いだろうなってて。物凄く掘り甲斐のあるジャンルだと思うんですよ、正直に言えば。金脈だなと思うし、今後も毎回舞踏を扱っていきたいとか思っている訳ではないですけど。単純にあんなに不安定なものはないからこそ、面白いと思っているんです、今のところ。
木村YouTubeとか見てると、海外のよく分からない人が自分のパフォーマンスを「舞踏」と名乗って、その動画のアクセス数がすごいものになっていたりすると、国際的にはこれが舞踏になっていく可能性があって、海外でカリフォルニアロール巻きみたいなものが寿司だ、となって流通していくみたいな現象が起こっていますよね。
長谷川大野一雄の『死海』を映像で見た時に、本当に笑えるくらい恐怖を感じたんですけど。何だろうこの映像はって。でもやっぱりそこで恐怖を感じて、そこで終わっちゃダメなんじゃないかと。そう感じた先というか、今は何故あれをああいう風にやっているのだろうとか、そうした側面から見れるので興味があるんですけど、初見の人がそこでアクセスを閉ざしてしまうのは勿体無いので、現代で上演をする以上、自身の作品はそういう様々な表現に出会う為の媒介になりたいと思いますし、現在性を持っていたいとは思います。
木村そういう意味ではあの作品は是非続けて上演してほしいなと思いますよね。
長谷川そうですね。舞踏といえば川口隆夫さんの『大野一雄について』とか今すごい回ってますよね。
木村だからあれは一つのやり方で、僕はあれを初めて観た時に、これは大野じゃないとか色々いちゃもんはつけられますよ、じゃなくてあれをやろうと思ったことに、すごい感動して。あと向雲太郎さんも駱駝艦出身なんだけど、彼も土方のYouTubeに落ちている動画を完コピして踊るというのをやったりして、あれも面白い。舞踏こそそういうものが徐々に生まれている場で、長谷川さんのもそういう一つになっていくだろうし。
長谷川でも舞踏の人たちが観る場では上演されていないんですよね。
木村いや、「完コピ」に怒った年配の観客から靴を投げられたって向さん言ってました。 でもそれも含めて面白い状況だと思うんです。
長谷川壷中天とかでも是非積極的に何かそういう試みをやっているのを観たいですよね、そういう意味では。
木村そうですね。でもちょっと話ずらすと、日本のコンテンポラリーダンスと呼ばれるものが、もう20年、30年くらい歴史を残している。ならば、舞踏を扱ったように、コンテンポラリーダンスを長谷川寧さんがああいう風に扱ったっていいんですよね。だから別に定型じゃなくてもいいんだけど、ダンスをシアターっていう箱の中に収めていくアイデアというのを、色んな人が色んなアイデアで試して、ダンスを観る視点を拡張していくというか、深めていくということがもっと起きたらいいなとい思っています。