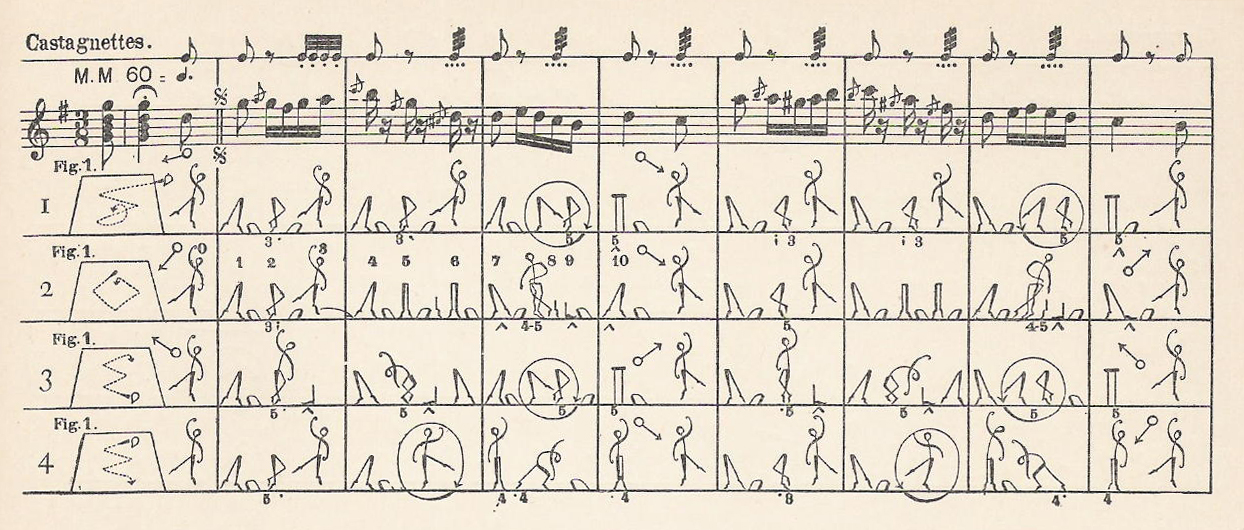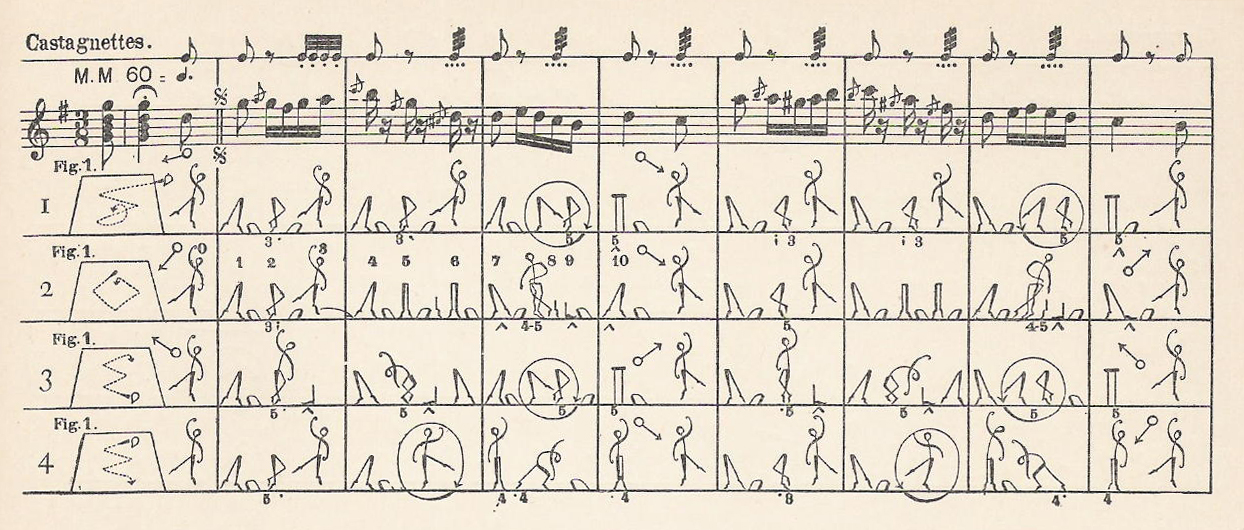2016/05/26
2020年のオリンピック、パラリンピックに向けて沸き立つ文化事業。なかでも障害者とアートを組み合わせたプロジェクトは、今後ますます増え、盛り上がりを見せることだろう。2020年以降の予算減額を見越して、このムーヴメントを刹那的な狂騒でしかないとする向きもあるけれども、何より大事なことは、障害者とアートの出会いを永続的な出来事と捉え、その未来を継続的に続いてゆくものとしてイメージし、具体的な方途を模索してゆく意志ではないだろうか。
今年2月にKAATで行われた「dialogue without vision」は、そうしたあるべき理想的な模索のひとつに映った。見えないダンサーたちがトライするコンタクト・インプロヴィゼーション。筆者がかつてレビューに書いたように、この舞台は単に「障害者も踊れます」的な上演とは一線を画すものであった。そしてまちがいなく、舞台芸術を更新するかもしれない新たな視点が含まれてもいた。この企画のように「障害」という要素と真摯に向き合うことが未来のダンスを、芸術をアップデートする力となるのではないか。
今回BONUSは、本企画のプロデューサー田中みゆきさんにお願いして、本企画を掘り下げる特集を進めてゆくことにした。まずは、田中さんのテキストで本企画の顛末を知るところから始めてみよう。
ちなみにシリーズとして
(2)「dialogue without vision」公演の映像 full ver.
(3)インタビュー集(振付家・康本雅子さん、出演者のみなさん)
と続く予定です。
障害に興味を持ったわけ
わたしが障害に興味を持つようになったきっかけは、義足だった。2009年に当時勤めていた21_21 DESIGN SIGHTで担当した「骨」展。この展覧会は、いわゆる生物学的あるいは物質的な骨を扱ったわけではなく、物事を構造や仕組みから見ることをコンセプトとし、Suicaの改札機のデザインで知られるデザインエンジニアの山中俊治さんと一緒に進めた展覧会だ。外装を外した日産フェアレディZやセイコーの腕時計、からくり人形師による仕組みを剥き出しにした弓曳き人形などを展示した。準備は2008年。それは、義足のアスリート、オスカー・ピストリウスが、史上初、健常者の記録を破った年だった。それがきっかけで義足の研究を始めた山中さんに、ある日ピストリウスの走る映像を見せてもらった。風を切って走る彼の姿は想像を遥かに超えて自然で、合理的な審美性がそこには確かにあった。その展覧会では当時SFC(慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス)で教えていた山中さんの研究室でつくり始めていた義足のプロトタイプも展示し、最後のイベントでは義足をつけたアスリートにミッドタウンの庭を走ってもらうなど、「新しい骨」である義足は重要な意義を持つものとなった。装飾や意匠ではなく、欠損した身体を補填し、物理的にはもちろんのこと、精神的にも身につける人に力を与える。義足はデザインの本質的な役割を問う、大きな可能性だと感じた。

2014年12月7日に日本科学未来館で行われた「義足のファッションショー “Rhythm of athletics”」/ Photo: Hajime Kato
そこからも義足に限らず障害のことには興味を持っていたし、施設を訪ねたりもしていたが、直接的に再び関わることになったのは、2014年に日本科学未来館で開催した「義足のファッションショー “Rhythm of athletics”」だった。義肢装具士の臼井二美男さんの主宰する陸上クラブに所属する男女11名による義足を見せるパフォーマンス。普段すれ違っているはずなのに、「社会の目」のもとに服の下に隠されている義足。少なくともわたしが出会った人たちは、周囲の心配や配慮をよそに、それぞれ義足に好きなファブリックを貼ったり、ペディキュアを塗ったりする楽しみ方を自分のものにしている普通の女の子たちだった。また、走るための義足や、ヒールを履くために足首の角度を変えられる義足など、わたしたちの脚はこんなに多くの機能を担っていたのかとしみじみ考えさせられるほど、機能や用途によってさまざまな種類の義足が存在することもわかった。そんな基本的だけれど知られていない重要なことをポップに紹介することを軸に、ショーを構成した。それらのことを知ることによって、わたしたちの身体が普段どのような構造で動き、それぞれのパーツがどんな役割を担っているか、そして脚というものが人の身体にとってどういう存在なのかを改めて考えることが狙いでもあった。
その時のつくる過程で一番心が動かされたのは、出演者の一人である藤井美穂さんという女の子の言葉だった。彼女は生後10日ほどで壊死した右脚の付け根部分を残し切断することになり、「ケンケン」でずっと暮らしてきた。家の外に出るときに義足をつけるのは親や先生のためのようなものと話す彼女はわたしに、「脚が二本ある意味がわからない」とあっけらかんと言った。わたしはそれは最高にクールなことだと思ったし、これまでに経験したことがないほど衝撃的な出来事だった。確かに、本人が満足していて日常生活に支障がなければ、そういう可能性だってあり得るのだ。思えば、わたしはそういう瞬間にもっと出会いたくて、今も障害のことを続けているのだと思う。
それ以外にも、しょうぶ学園という鹿児島の知的障害者支援施設の利用者とスタッフで構成されたバンド「otto & orabu(オット・アンド・オラブ)」とアーティストの高木正勝さんによるライブを行ったり、ブラインドサッカーや車椅子バスケの選手とワークショップを行ったり、いろんなかたちでさまざまな障害を持つ方々と関わってきた。そこでわかったのは、当然のことながら、本人たちは不便なこともあるかもしれないが、それは不幸を意味するわけではないということだ。例えば、障害の事情についてあまりよく知らない第三者が、「障害に”害”の字を使うのは配慮が欠けているのではないか」と言うのをしばしば耳にする。当事者がそう主張するのであれば考えるべきことだと思うが、何か行動を起こす前から始まる周りの過剰な配慮がかえって社会における障害を生み出していることも現実としてあると思う。障害には、それが個人の身体的な状態や症状に由来するという「個人モデル」や「医療モデル」と呼ばれる考え方と、社会との関わりが障害を生み出すと考える「社会モデル」がある。わたしは障害について知ることは、世界をそれまでとは違う視点から捉え直すことだと思っている。そしてそれは社会を後退させるのではなく、これまでこぼれ落ちていた「そういうことだってあり得る」という可能性を一つひとつ考えていくことになると思うし、それが社会を「豊か」にすることだと思っている。そういう意味で、わたしはアートやデザインという手法を使って障害のことを考える機会をつくり、それぞれが社会の豊かさを考えることにつなげていきたいと思い活動している。
「イメージ」から自由であること
これまで何度か参加させていただいた活動に、「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」というものがある。それは、美術館や文化施設の中で、視覚に障害がある人たちと一緒にいくつかの作品を見て、言葉を交わすワークショップだ。そこに参加している視覚障害者は全盲の方が多く、作品を目で「見る」ことはできない。ただ、そのワークショップは目で見ることのできない人に見える人が作品を教えてあげるというものでは全くなく、目で見えない人は見えないまま、見える人は見えるまま、お互いが得ている情報やそれについての印象や疑問を主に言葉でやり取りするというものだ。目で見ていない人は、例えばなぜその絵に描かれた街灯は普通と違う色をしているのかなど、作品にとって重要な質問を素朴な疑問として投げかける。それに答えることを通して、見ている人は改めてその作品と向き合うことになる。それだけでなく、時に見えていると自明のものとしてやり過ごしてしまう基本的な情報(大きさや配置など)について質問され、当たり前に前提としていたその情報が実は作品を規定する大事な要素だったことに気づかされたりもする。
それらの経験を通してわたしが感じたのは、視覚に障害があるということは、「イメージ」から自由であるということだ。それは、視覚情報という意味ではなく、見えているから見過ごしてしまう固定観念や思い込みのことを指す。ただ、それを「自由」と捉える前に、見えない状態は目の前の物事に効率よく対処することに対しては不自由そうに見えるため、周りの健常者たちが気を揉み、予めいろんなことを制限してしまっているのが今の社会だと思う。出演者探しをする中で、若い女性で街を一人で自由に歩いている視覚障害者が少ないことも改めて気になったが、学校で運動を始めとして健常者と同じことをするのを試みる前に制限されてしまうケースも多々あるようだ。例えばある特別支援学校にダンサーがダンスを教えに行った際、生徒の身体に触らずにダンスを教えてくれと学校側から言われたという話も聞いたことがある。
程度の差こそあれ、何かしら周りの配慮によって行動を制限されているとしたら、そんな彼らが、これまで試みる機会の少なかった「思いきり身体を使う」という感覚が開かれたときに何が起こるか見てみたかった。もちろん日常生活において人は8割から9割を視覚情報に頼っていると言われ、そこに障害があることによって生じる不便さが何かしらあることは否めないだろう。ただそれは社会がその障害に対応する選択肢を用意できていないだけで、そのことが彼らの生活の「豊かさ」をすべて奪っているかと言うと、必ずしもそうとは言えないのではないか。他者との関係をつくったり、世界を知ったりすることにおいて、視覚だけが唯一の手段ではないのだから。
「作品」はつくらない
このプロジェクトを始めるときから決めていたことがあった。それは、「このプロジェクトの目的は、作品をつくることではない」ということ。どういうことかと言うと、誰か一人のアーティストの完成された作品の中に障害を持った人を登場させる、あるいはその作品を彩る要素として障害が使われるといったことは避けたいという強い思いがあった。また、社会における障害を考えていくために、一人でも完結しうる表現を追求するのではではなく、相手があってこそ成立する「コミュニケーション」を扱うことにした。今回はスペクタクルではない、どちらかというとパーソナルなものにしたかったし、パフォーマンスの中で帰結せず、どこか開いたものにしたかった。そのことは最初から関わるアーティストには伝えていたし、関係者は全員視覚障害者と関わることが初めてのスタッフを選んだので、必然的に出演者と一緒に試行錯誤し、視覚障害について学びながら、つくっていくプロセスを辿ることになった。

最初のワークショップで話をする康本雅子さん
今回のパフォーマンスは、康本雅子さんと二人でかなり頻繁に連絡を取り、意思疎通を図ったり企画意図を何度も議論したりしながらつくっていった。毎回ワークショップや稽古が終わると打合せをし、次の日以降にまた電話でお互い思ったことを話し合い、次の稽古に備えるという小さな積み重ねだった。康本さんの役割は、振り付けではなかった。出演者が動くことに対する抵抗をなくし、身体を動かすときの引き出しを増やすこと。そして一番重要なことは、身体を使ってコミュニケーションするとはどういうことかを身体で覚えてもらうことだった。康本さんと企画について話す中で、比較的最初の段階から「コンタクト・インプロヴィゼーションをやろう」ということが康本さんからの提案としてあった。「普段視覚を使う割合が小さいとすると、触ったりして確かめることが晴眼者よりも多いのではと思ったから」と康本さんは言う。わたしも「振りを覚えるのではないものをつくりたい」というのは最初からあった。もう一つ、テクノロジーの発展により、障害の概念そのものや障害へのアプローチが変わろうとしている時代背景を受けて、テクノロジーを使いたいというのもあった。
完成形を想定せずにつくり始めること。その上で今回一番の肝となり、一番苦労したのが、出演者集めだった。特別なダンスの才能を持った人や、既に特定のダンスを身につけている人というよりも、「普通」の視覚障害者にこだわりたいと思ったため、芸術への関与は問わず、純粋に音に反応して身体を動かすことや新しいものをつくることに興味のある人を募ることにした。先述の「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」やブラインドサッカー協会など、わずかでもつながりがあるところにお願いに行ったが、アートに興味のある人は身体を動かすことに興味がなかったり、スポーツに興味のある人は今回のように敢えて分けるなら表現に近いものには興味がなかったり、これは障害の有無は関係ないが、体育会系/芸術系の壁というものが立ちはだかった。

最初のワークショップでペアワークを行う加藤秀幸さんと樋口匡さん
そして、「コンタクトインプロ」という手法をどう視覚に障害を持つ人に伝えるか、というのが次の壁だった。例えば、先天性ではなく、途中で視覚障害を患うようになった人は、「ダンス」のイメージは持っている。ただ、今回やろうとしていたのは、いずれにせよ決まった振りを覚えて上手く踊れるようになることではない。そもそも視覚に障害がなくても、ダンスの世界に全く触れてこなかった人にとっては何も見ずに理解するのは困難であろうアプローチを、視覚障害を持った人に伝えることは至難の技だと思った。それに「テクノロジー」が加わると、相手側に「一体何をされるんだろう」という不安感・不信感が募るのがこちらにも伝わってくる。そこで、詳しい説明は省き、身体を動かすことにポジティブな人且つ、他の人と一緒に何か新しいものをつくることを面白いと思える人、という非常にざっくりした説明をして、興味を持ってくれた人にとにかくワークショップという形での導入に参加してもらうことにした。そしてこれまでの繋がりや視覚障害者と映画を楽しむ活動などを行っている知人に周知してもらうことで、出演者の2倍を超える方たちにワークショップに参加してもらったり、問い合わせをもらったりすることができた。
ワークショップでは、康本さんのファシリテーションにより、身体をほぐすところから、身体で相手とコミュニケーションをとるさまざまな方法を体験してもらった。例えば弱視の人も目を閉じて、ペアになったり全員でつながったりしながら、声を出さずにお互いの気配で腰を下ろしてしゃがんだり、起き上がったり。ペアの片方の人が立ち、もう一人の人が相手の身体を自分の身体を使ってなぞっていったり。その時点で、手のひらだけを合わせて動く、より広い身体の部分を接触させたまま動く、という本番の原型となる断片は既にあった。少し動いてみる度に参加者の感想を丁寧に聞いていくことは、わたしたちにとっても学び多いことだった。手のひらを合わせて動くだけで相手の体格や性別、性格なんかも何となくわかってくるという手のひらから伝わる情報の多さの話や、とりわけ新鮮だったのは、「これまでは誰かに誘導されて動くことが当たり前だったけど、(自分が主導権を握って)誰かを振り回すことは初めてで気持ちよかった」というものだった。コンタクトインプロのアプローチを続けることはお互いにとって何か収穫があるかもしれないという手応えのようなものがあった。
視覚障害についての誤解
「視覚障害」というと、一般の人は全盲を思い浮かべることが多いのではないかと思う。しかし、全盲は視覚障害者全体の1割弱しかおらず、弱視と呼ばれる人たちの方が圧倒的に多い。彼らは視界の一部が欠けていたり、明暗の差に大きく影響を受けたりという、他者からは一見わかりにくい障害を抱えている。また「弱視」と一言でいってもその種類や見えにくさは多岐に渡り、ある特定の環境下や行為においてならばさほど不自由することはない弱視の人もいる。そういった人たちは周囲からは見えていると思われてしまうため、いざ補助が必要になったときに必要な補助が得られなかったりする。「視覚障害者=全盲」というのは、視覚障害に対する根深い偏見の一つ。今回も、恐らくわかりやすさを追求すれば、全員全盲にするという選択肢もあったかもしれない。ただ、社会はそんなにわかりやすくできていないし、結局は視覚障害に限らず、画一的な「障害者」など存在しない。それぞれ違う症状を抱え、対処法を模索しながら障害とつき合っている個人だ。結局は、元々の個々の違いの一部に障害も含まれているに過ぎない。そのことを踏まえ、障害の程度は出演者選びにおいてそれほど大きな基準にはならなかった。それよりも、どれくらい他者とコミュニケーションをとることに好奇心を持てるか、とことん相手と向き合う気持ちがあるかの方が重要だった。結果、先天性全盲1名、中途失明の全盲1名、それぞれ違った見え方の弱視4名という構成になった。

デバイスのテストを行う加藤秀幸さんと筆者
それぞれ全く違った個性や障害を持った6名だが、先天性全盲の加藤秀幸さんには制作のプロセスで特に深く関わってもらう場面が多々あった。加藤さんは光を感じ取ることもできない生まれながらの全盲で、システムエンジニアとしても働き、ミュージシャンとしても活動している。過去に高嶺格さんがせんだいメディアテークで行った視覚障害者がガイドして巡る展示『大きな休息』(2008年)のガイドをしていたこともあり、「加藤さんってあのブラインドタッチが凄い人だよね」と高嶺さんも加藤さんのことをはっきり記憶しているほど、人の印象に強く残る何かを持っている。また、ものづくりをしていることもあり、「つくる」ことについての理解も深い。加藤さんという視覚障害の度合いの面でも活動の親和性においても極端で貴重な存在がいてくれたからこそ、ステージでのスピーカーの置き方や方向性、変化を把握しやすい音の選び方についてなど、的確なアドバイスをもらいながら進めることができた。
テクノロジーと障害
実は最初に思い描いていたものは、もう少しテクノロジーオリエンティッドなものだった。デバイスやセンサーを駆使して、視覚障害を持った出演者たちがお互いにぶつかったりせずに舞台上を自由に動き回ったり、目的地にたどり着いたりすることを演出として取り入れようと考えていた時期もある。理由は、元々わたしがデザインを出発点としているため、「作品」をつくるのではなく、何かしら日常生活の延長としてパフォーマンスを捉え、彼らの生活に役に立ちそうな要素が取り入れられたらという思いが根底にあったためだ。あと、彼らが健常者にはできないことができることを見せることが何かしらの価値になるとその時点では思っていたのだと思う。それは、出演者と稽古やテストを進めていくなかで大きく変更していくこととなる。
健常者の障害者に対する先入観の中で、悪気はないのに偏見となりうるのは、「障害を持った人はみんな(障害を抱えている分)他の何かの能力が突出して優れているはずだ」という思い込みだと思う。「視覚に障害がある人は特別耳が良いはずだ」などというのがその例だ。上に書いた全盲と弱視の違いもそうだが、先天性か後天性かでも障害の状況は全く違う。先天性の場合は、確かに視覚以外の感覚を頼りに生活をしてきたこともあり、そうではない人よりも鋭い聴覚を持った人が多いといえるだろう。しかし後天性の場合、特に成人後に視覚障害になった人については、視覚があった頃の記憶と関連させて物事を認識していることも多いし、触覚や匂いなどその他の感覚と合わせて複合的に認知しているため、必ずしもそうとは言えない。障害を持っていない人は普通にいるだけでもそれぞれの個性やキャラクターを生かして生き方や道を選ぶことができるのに、障害があると途端に健常者とは違う特別な存在であるかのように過度な期待(それも偏見の一つ)を持ってしまうことについては、気をつけなければいけないと思う。繰り返しになるが、障害はその人が育ってきた環境や条件の一部に過ぎないのだ。
11月に公演で使うデバイスの最初のテストを行った。その時点でのスズキユウリさんからの提案は、会場の横幅と奥行きの二軸にセンサーを張らせ、音をマッピングし、その中を出演者が移動するとその位置に応じてさまざまな音が鳴るというものだった。ただ、テストをしてみると、結局位置が音を規定するので、センサーの範囲を右往左往したところで、人によって違いが出るわけではない。音により位置が把握できるようになる可能性はあったが、むしろセンサーの範囲が彼らの動く範囲を規定しかねないことと、その範囲から出てしまって音が鳴らない状態が「間違い」のようにも見えてしまうことがわかった。そのため、ステージ側ではなく出演者側にセンサーを付けることで、出演者の動きを終始制限しないように修正することとなった。また、発した音の反射音から対象物の方向性や距離を読みとる「エコーロケーション」を再現しようという案もあった。ただ、それを再現するには、出演者が的確に壁の反射音を受け取ることができる完璧にコントロールされた空間が必要だ。そして、再現できたとしても、全盲ではない出演者や観客の大多数の健常者が今度はその状況を共有できない。今回のパフォーマンスは劇場ではない、オープンスペースということが前提としてあったため、その方向性は追求しないこととした。

「dialogue without vision」上演の様子 / Photo: Ryuichi Maruo
テクノロジーと障害の関係については、これから2020年に向けてますます多くの研究者やクリエイターが関わっていくことになるだろうと思う。義足を始めとする義肢についても、筋電義手という筋肉に発生する筋電位を使って操作するものや、足首部にモーターを搭載してより人間の歩行に近い状態を再現するロボット義足などの研究も進んでいる。今回は出演者が決まってからの制作期間が約3ヶ月弱と非常に短いものだったため、本番自体もデバイステストのような形で、プロトタイプとして非常にミニマムな要素で臨むこととなった。ただ今回のプロセスの中で感じたのは、完成形が見えてからそれを障害者に合わせて調整していくのではなく、開発の早い段階から彼らを巻き込んで、本質的にテクノロジーが彼らの何を補ったり引き出したりできるのか、そもそもテクノロジーが必要とされているのかということからとことん議論することの重要性だ。実際に、彼らもモニターとして商品を使って感想など求められる機会も多いが、大体がほぼ完成したものについて、どうすれば使いやすくできるか意見を求められるという。ただパフォーマンスがプロダクトやサービスの開発と違って難しいのは、大抵の場合観客には健常者が圧倒的に多いことを想定すると、まずは障害を持った当事者が面白いと思えて、健常者もそれを何らかの形で共有できる仕組みや使い方の設計が必要となる点かもしれない。また、今回は視覚障害を持つ観客のための音声解説を取り入れたが、作品に対しての感じ方は自由とは言え、作品を理解するための多様な情報提供の方法は今後もっと検討されるべき事柄だと思う。

Photo: Ryuichi Maruo
衣装については、シアタープロダクツの金森香さんと最初に打合せをする中で「フードなんか面白いかも」というキーワードが何となく出てきたことが始まりだった。それを聞いた時、盲の状態とフードの相性の良さを直感的に感じた。その時点では出演者も決まっておらず想像の世界でしかなかったので、『ダイアログ・イン・ザ・ダーク』で何度か体験したわずかばかりの感覚をたぐり寄せたときに、見えない状態は、顔にぴったりと目隠しをした状態よりも、フードをすっぽりかぶったようにある程度の余白はあるけれども身体と境界の手がかりがわからなくなる感覚の方が近いと思った。フードを主につくっているこんなブランドがあると紹介してもらったのが、衣装協力をお願いしたhatraさんだった。「ポータブルな家」という発想でつくられた大きなフードは、プライベートとパブリックの間を漂うものとして、演出上も欠かせない要素となった。
もう一つ重要な要素として、ステージの境界に敷いた点字マットがある。偶然立ち寄った視覚障害者のための生活補助用品の展示会で目に留まった鮮やかなピンク。近づいてみると、次世代のバリアフリーの提案としての視覚障害者用誘導マット「HODOHKUN Guideway」というものだった。白杖でやわらかいマットを確認して目的地にたどり着ける歩行誘導マット。弱視の人も認識しやすいカラー展開で環境とのコントラストが強調されている。従来の点字マットは車椅子やベビーカー、点滴の車などの邪魔になるため法律で規定された場所や最低限の公共施設にしか設置されていないことが多かったが、これであれば誰の障害にもならず、必要な人に必要な情報を届けることができる。何よりこれまでの福祉的なイメージを覆そうという思いを感じる鮮やかなピンクが良いと思った。製作元の錦城護謨さんも、ほとんどの稽古に立ち会い、本番と同じようにマットを敷いて環境を整えてくださった。出演者が視覚に障害を持っている場合、特に立ち位置や曲がり角などの動線において、本番と稽古の条件を整えておくことも非常に重要だった。
本番に至るまでのいろいろな決断
稽古はオーディションを兼ねたワークショップも含めて全部で7回行った。基本的にはコンタクトインプロをやりながら身体による対話のバリエーションを促したり、ペアを変えながらペア同士の相性を見たりしながら進めていった。動きの練習というよりも、出演者同士やスタッフとの関係性を築いていく期間だったとも言える。
今回一つの大きな議論として、「弱視の4人は普段通りの視覚の状態でパフォーマンスに臨むかどうか」ということがあった。もともと目を開けたままにすると、外からは健常者と区別がつかないことで観客に混乱を招くのではないかという懸念が企画側としてはあった。同時に、コンタクトインプロを使って稽古を行う中で、出演者から「目を閉じた方が集中できるからやりやすい」という声も出ていた。というのも、全員健常者と同じだけの視野の範囲はないものの、弱視の出演者にとっては逆に「ない部分がある」からこそ、目を開けていると残された「見えている部分」に過度に意識が集中してしまうということだった。目隠しをする、ゴーグルをする、目を開けたままにする―これについては本当に何度も出演者と話し合った。その結果、今回のテーマである身体を使ったコミュニケーションを行うのに出演者が最も自然でいられる状態を選ぶことになり、弱視の4人は目を閉じることとした。

Photo: Ryuichi Maruo
パフォーマンスの構成も、康本さんと話しながら決めていった。視覚障害を持った人たちによる身体を使ったコミュニケーションであるということを最初に直感的に伝える必要があると思った。そのため冒頭には、出演者が健常者と違うモードで空間や他者とコミュニケーションをとっていることをわかりやすく伝えるためにテクノロジーを導入することにした。一つはテストの反省を踏まえ、出演者が身につけた距離センサにより対象物との距離に応じて音階が変わるもの。もう一つは加藤さんがいつも使っているPCの音声読み上げ機能。健常者だと通常は視覚的に判断するアプリの立ち上げから入力、改行などあらゆる操作がすべて音声で読み上げられるものだ。公演での再生速度は実際に加藤さんが普段使っている速度より数倍遅くして、健常者が聞き取れるか聞き取れないかくらいのところで再生した。
その後のパフォーマンスでルールとしたのは、ステージに入る時/出る時と動き出すときの合図を特定の音で知らせること、出番が来るまで待つ立ち位置、衣装であるhatraのパーカーを脱ぎ着することでパフォーマーとしてのスイッチをオン/オフすることだった。それ以外、例えば出演者の動き方や最後のペアが終わるタイミングなどは全て出演者に任せた。そして、基本的に二人一組となって行うパフォーマンスの相手は事前には知らせず、毎回変えることで、ステージ上で出会って身体を触りながら確かめてもらうことにした。もちろん6人なので組み合わせには限界があったが、そうしたことで毎回何かしらの予期せぬハプニングがあったし、面白い瞬間も、そうではない瞬間もあったと思う。そして、毎回誰かしらが何かを間違えたりして、完璧な回はなかった。それが個人的には良かったと思っている。
プロセスの後半でよく考えたのは、「今回のパフォーマンスは(健常者による障害者の)搾取になっていないだろうか?」ということだった。「生まれつき視覚のない加藤さんが何を頭の中に描きながら踊ってるか覗いてみたいよね」ということを稽古のプロセスで何度か第三者に言われたりした。ただ、それを加藤さんの話を聞きながら再現したとして、それを加藤さんは見ることなく健常者だけで共有することは違うと思った。また、特に振り付けもなく、身体を使ったコミュニケーションをしてもらうことをゴールとするならば、十分彼らはそれを達成している。ただ、観客の立場になると、そこに何かしらの視覚的な面白さを求めてしまう。上演後の感想もそれについてのものが多かった。そのことについては、根底にあるのが「舞台上にいる彼らは見られないのに、観客は一方的に彼らを見ている」というある種の暴力性とも捉えられかねない関係性があったからではないかと、終わった後、康本さんと話したりもした。『義足のファッションショー』もそうだが、普段社会に隠されがちな障害者、それも一人ではなくそれぞれに違う障害を持った人たち、を一同に見る機会として彼らの身体をできる限りそのまま見せることが目的の一つだったので、今回の場合は特にそういった暴力性を予め含んでしまっていた部分もあっただろう。わたしたちの日常生活がそうであるように。
わからないまま一緒にいること
今回の公演をTPAMの期間中に開催したことで、見に来ていただいた方たちの期待に応えられていたのかは正直なところわからない。実際に、康本さんが出演者に振り付けをしたと思い込んで見に来られた舞台関係者は少なくなかったようだし、きっとそう思って見られた方がわかりやすい人もいるのだろうとは思う。ただ、個人的に思うのは、いわゆる「作品」としての発表形式が公演とすると、そうではない形のアウトプットは「ワークショップ」しかないのか?ということだ。今回最後まで康本さんと議論になったのは、最後の終わり方をどうするかということだった。当初康本さんからは、例えば出演者が最後客席に出ていって、観客を巻き込んでコンタクトインプロをするのはどうかという案も出ていた。理由は、コンタクトインプロは見るのではなく一緒にやるのが一番実感を持てるし、実際にワークショップで彼らと組んだ時に思いもかけないところを触られたりした経験は忘れがたいものがある。ただ、そこで観客が参加して何かワークショップ的な終わり方で「わかった」ような空気になることは、今回伝えたいことではないのではないかと思った。また、そこで舞台に出る/出ないことがその人の答えでもないと思った。

Photo: Ryuichi Maruo
つまり、わたしは今回出演者と接する中で、「わかる」ことがゴールではないと思っていた。視覚障害の疑似体験をするのであれば、暗闇の世界を体験する『ダイアログ・イン・ザ・ダーク』に勝るものはないと思う。そして、「視覚障害ってこういう状態なんだ」と実感できることは、何も知らないよりも大きな一歩だが、それがそのままお互いを尊重し共存することには必ずしもつながらないと思う。むしろわからないままに心を通わせる可能性だってあるし、大切なのは、自分との違いを受けとめ、それを含めて相手とどう面白がって向き合うことができるかではないだろうか。障害を持った人を匿名の「障害者」として画一的に扱うのではなく、個人として向き合ったときに、障害という違いはその人たち同士のたくさんある違いの中のほんの一部でしかないのだ。
最初に書いた藤井さんの「脚が二本ある意味がわからない」の名言に匹敵する場面が今回もあった。スタイリストの髙山エリさんが加藤さんの衣装であるピンク色のパーカーに合わせて同じ色のズボンをつくってきたときに、出来上がった興奮から髙山さんが「加藤さん、見てみて、つくってきたの!」とズボンを広げて目の前で見せたときのことだった。加藤さんはすかさず「俺見えねーし」と返して、その瞬間その場がみんなの大きな笑いで包まれた。それは、時間をかけて制作チームが家族のようになっていったからこその出来事だったと思うが、自分にとってはかけがえのない瞬間だった。実際に康本さんとの制作打合せも、前半はそれぞれの障害にどう対応するのが良いかについての話題が多かったと思うが、後半は完全にそれぞれの性格や癖に関することが中心だったように思う。そういうことがあちこちで普通に起こっていけば、少しずつ社会は変わっていくんじゃないかとわたしは思っている。
残念ながら、普通に生きていてそんなふうに障害を持った人と関係を築ける機会がそんなにある訳ではまだまだない。「視覚障害=全盲、盲導犬、白杖」くらいの認識しか大抵は持っていないであろう観客に対して、「公演」というかたちで「障害」や「障害者」を扱うということは、やはりある程度スペクタクルにせざるを得ないのではないかというジレンマもある。それでもわたしは、今後も障害と向き合っていきたいと思うし、わたしたちが辿ってきたプロセスが、少しでも今後の障害を扱ったパフォーマンスの制作に役立てることができればと思い、ここに記そうと思う。