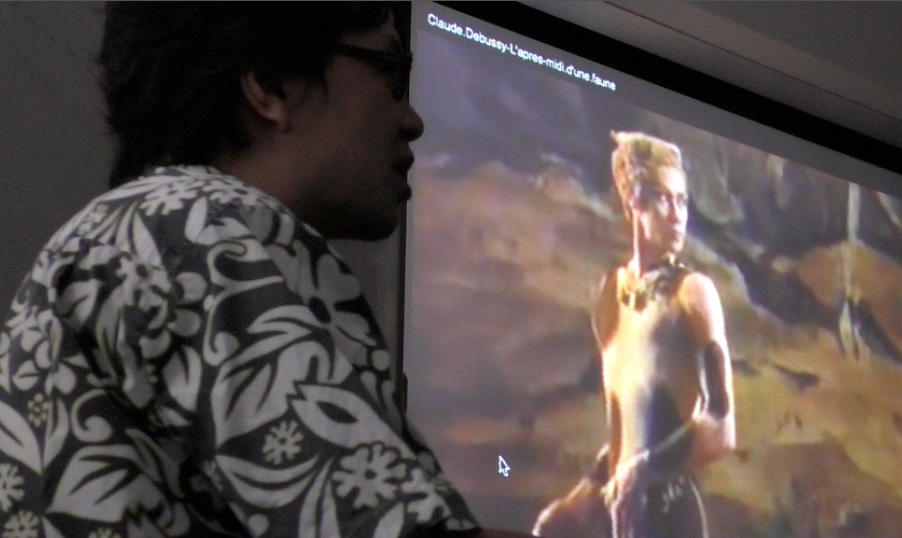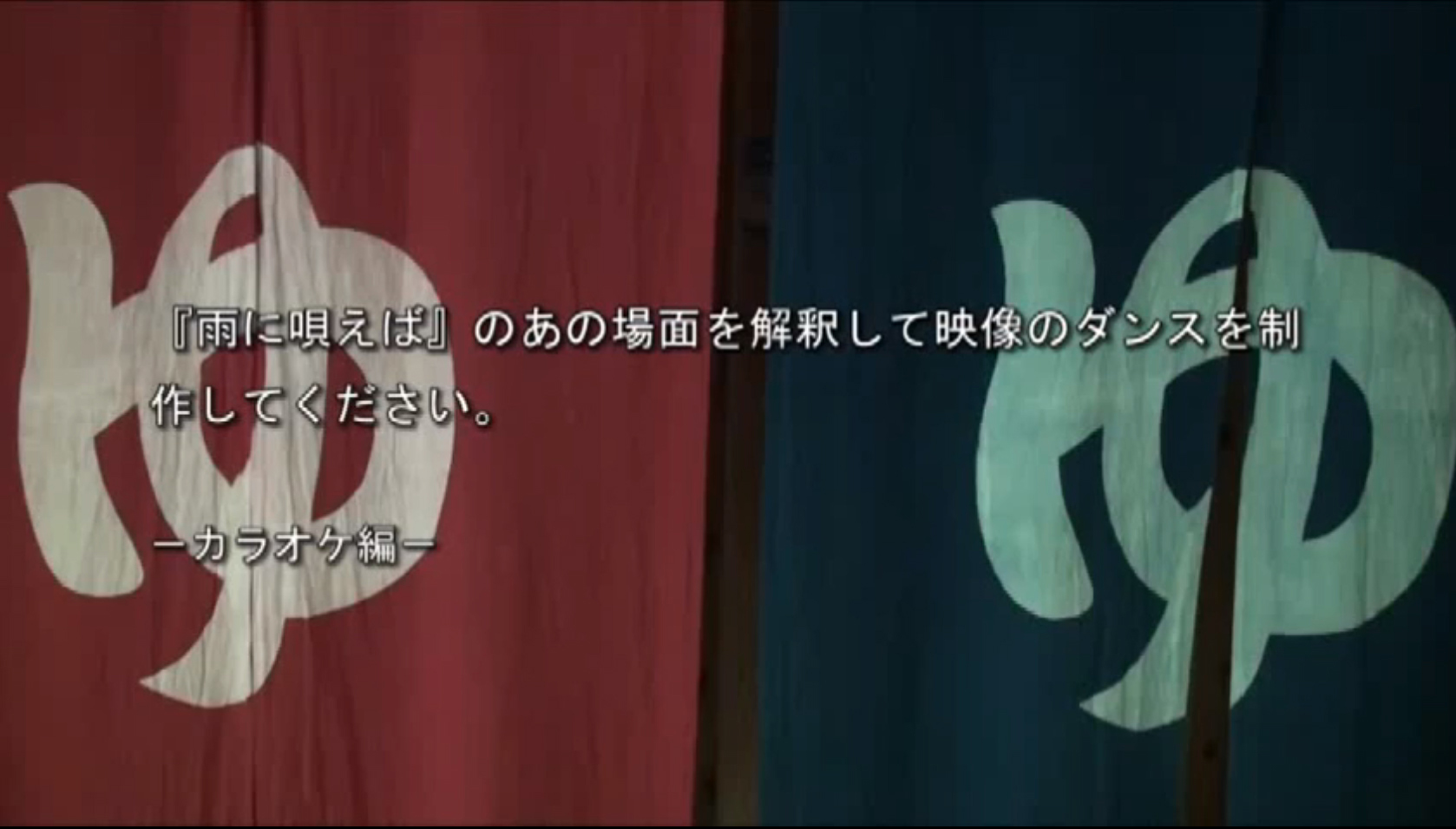2015/12/12
はじめにBONUSの主催者である木村覚氏より、「障害(者)」と「ダンス」を掛けあわせたパフォーマンスのプレゼンテーションを行うイベントにコメンテーターとして参加して欲しい、というメールの依頼を受けたとき、正直に言えばむしろ私は躊躇し、不安を覚えました。少なからずの人々が障害者アートに関心を抱いていて、関西ではダンスセラピーを実践している熱心なダンサーたちや音楽療法を使ったイベントも少なくなく、もっと相応しいコメンテーターがいるのではないだろうかと感じました。それゆえ、木村氏への返事のメールでは、その旨を書いたうえで、より相応しい人がいるはずだということも提案しました。
私は、心理療法と芸術学の交叉を扱う甲南大学人間科学研究所で、博士研究員としてアートとセラピーの「歴史」について調査してきましたが、ダンスの専門家でも、いわゆる「障害者アート」の専門家でもありません。むしろ、個人研究の方向を、精神疾患のひとつと見なされている PTSD(ポスト・トラウマティック・ストレス障害)やトラウマ的記憶に焦点をあわせていました。たしかに傍目からは隣接領域に見えるかもしれないし、もちろん重なる部分もありませんが、おそらく今回「障害(者)」として想定されていると思われる「身体障害者」や「知的障害者」とは異なる心理学とアートの歴史について考察してきました。とはいえ、今回の会に参加することを引き受けようと思ったのは、木村さんに私の研究関心が身体とメディアの関係にあるときわめて的確に指摘いただいたこと、さらに場違いな状況を楽しんでみるのも良いと考えたからです。
「障害」という言葉は幅広く、身体的な損傷から精神的な障害(disability だけでなく disorder も含まれます)、さらには重度・軽度によってかなり幅がある事柄をひとくくりにした概念です。思いつくままに列挙してみても、身体障害、視覚障害、聴覚障害、統合失調症、認知症、発達障害などがあり、それぞれまったく違う身体性が想定されるでしょう。むろん「障害」認定によって福祉サービスを享受できる程度を判断する社会制度の枠組みがあり、そこには上記のさまざまな「障害(者)」が含まれていることはたしかです。生まれつき障害を被っているという場合から、人生の途上で事故や病気など何らかの事情で障害者になる場合、さらに人生の晩年に病気を抱えターミナル・ケアのなかで障害を抱えつつも生きつづける場合も含まれます。このように広範囲におよぶ「障害」という概念をひとつの舞台に乗せようとすれば、話が深まるどころか、それぞれが思い描いている言葉の定義や認識の違いで議論が堂々巡りになってしまうことは目に見えているように思えました。あるいは、アートを通した障害者やその支援者へのレクリエーションや、アートによっていっそうの社会的包摂(インクルージョン)が可能になるといった漠然とした「アート力」の賞賛に終わってしまうかもしれません。私はこれらの取り組みの意義や効能を認めるのにやぶさかではありませんが、障害者とアートという題目を耳にするとき、言葉の暴力とまでは言わないにしても、しばしば乱暴なものを感じることも確かです。再度、木村さんの依頼のメールを読み直すと次のように書いてありました。「障害者の身体は、単に欠損ではなくて、健常であると思い込んだ人間が忘れている身体の可能性を教えてくれるものかもしれないと思うのです」。あえていうならば、この一文にも少し違和感があります。「障害」をどのように定義するにせよ、「欠損」というよりは「過剰」と言えるのではないだろうかというのが私が日頃感じていることです。車椅子に乗ったり、杖を持ったり、盲導犬を連れたりして日常生活を送っている障害者の身体性は、むしろ衣服まとった日常的な身体に、過剰な道具やテクノロジーに頼りながらも、上手にそれらを使いこなしながら生活を送っているように見えます。また知的障害者の場合でも何らかの精神的な働きが過剰に働いて、日常的な社交性やコミュニケーションにかえって適応できなくなってしまう場合があります。過剰な道具やメディアを使って日常生活に適応している存在だからこそ、特異だったり突出したりしているように見えるために、私たちが「忘れている」というより、まったく未知の可能性を秘めた存在に見えるのではないのでしょうか。
上記のような考えを整理するためにも、少し長くなりますが生命の環境への適応という観点から、人間の「正常」と「病理」という科学の概念を歴史的・哲学的に考察したジョルジュ・カンギレムの議論を再読しておきたいと考えました。カンギレムのテクストは第二次世界大戦後まもなく、つまりは「障害者」が不当に社会から隔離されていた時代に書かれたもので、正常と病理や異常や奇形といった科学に対して鋭い考察を加えています(彼の議論はミシェル・フーコーやジル・ドゥルーズらポスト構造主義哲学に大きな影響を与えました)。カンギレムは「人間的な生命は生物学的な意味、社会的な意味、実存的な意味をもつことができる」と述べ、生物学、社会学、哲学、それぞれの角度から、正常と病理について考える必要を主張しています。カンギレムは以下のように言っています。「人間的な生命は生物学的な意味、社会的な意味、実存的な意味をもつことができる。病気が人間の生体に加える変容についての評価において、それらのすべての意味が区別されずに考慮に入れられる。人間はただ木とかウサギと同じように生きているのではない」と(ジョルジュ・カンギレム「正常なものと病理的なもの」『生命の認識』杉山吉弘訳、法政大学出版局、2002年、180頁)。障害や病理的な身体と正常や健常とされる身体の境界を考えるさいに、カンギレムの言う生物学的、社会的、実存的な意味を確認しておくことは重要だと思います。ここで彼の議論を、適宜、芸術史の文脈を補いながら大雑把に概観しておきましょう。
統計学における特異性と理想からの欠損
カンギレムは、19世紀の実験医学が成立するなかで〈正常 normal = 規範にかなった〉という概念は次の二つの特性を生命的な有機構成に結びつけることによって矛盾や混乱を免れえなかったと指摘しています。一方は、統計学的な調査によって記述可能な事実としての、単なる偏差、変異としての不規則性や特異性(anomalie)=「不均等、水準の差異」(グザビエ・ビシャ)であり、他方は、「失敗、欠損、不純なもの」としての病理的な変質(クロード・ベルナール)のあいだの二つの特性です。単なる統計学的な偏差に過ぎないものが、失敗や欠損と見なされるのは、典型あるいは完全な形態という意味でのプラトン的な理想の概念がそこに暗に想定されているだろうというのが、カンギレムの指摘です。こうした考えを芸術史の文脈で補うならば、19世紀に、芸術家の役割を説明するのに〈天才genie〉という言葉が盛んに使われはじめたことに関連します。というのも時代や環境を変容させる役割が芸術家の特異性に帰されると見なされはじめたからでした。それらは、20世紀後半に向かうと逆に病理的な変質に近いものとして捉えられるようになっていきます(ちなみに印象派の筆触分割について、当時には色覚異常や変質として病理的なものと見なす批評言説がありました)。つまり、近代以前は、狂人にも類することもできる道化と考えられていた芸術家の役割は、近代初頭に天才として積極的に評価されたにもかかわらず、20世紀に向かうにつれて病理的な変質の概念と混じりあっていきます。とりわけ優生学の勃興によって、そうした変質は社会や文化から排除される一方で、シュルレアリストらの芸術家や擁護者たちは、正常を超えた幻視者たちの能力を積極的に擁護していくという逆説がはじまったのでした。
病理の生物学的意味とその時間性
カンギレムは19世紀に基盤となりはじめる実験医学の成立期における正常と特異性の概念を確認しながら、生命の発生学における進化論的な特異性ついて議論を進めていきます。すなわち生物学的な障害の意味と環境への適応の関係をとりあげます。そこで例となるのは、卵の成長メカニズムに関するエティエンヌ・ヴォルフの発生学の研究例です。その研究によれば、発生の段階で「成功した形態」と「失敗した形態」のあいだに差異があるわけではないということです。カンギレムはその事実から次のように述べました。「すべての成功は、諸個体が死ぬがゆえに、また種さえ死ぬがゆえに、脅かされている。成功は延期された挫折であり、挫折は流産した成功である」。さまざまな生命の形態が、必然的な死や病理を延期させるという「時間の幅」によって正常と異常の境界が定められるようになります。この考えでは、永遠的・超歴史的な原型(アルケタイプ的)な理想ではなく、時間的・歴史的な祖型(プロトタイプ的)な環境への適応の条件が、正常と異常という区分けを可能にするとみなされます。つまり、私たちは産まれる時から病院の保護的な環境のおかげで授かった生を安全に生き長らえさせることができています。環境に起因する病気、事故、がんなどの病気を被り障害者となることを延期させながら生きていると言えます。この場合、仮に「健常者」ということが言えるとしたら、単にまだ「障害者」になっていない人ということを意味することになるでしょう。
テクノロジーによる社会適応と不適合としての精神疾患
カンギレムは、進化論において「環境によるふるい分けは、あるときは安定した状況において保守的であり、またあるときは危機的な状況において革新的である」ことも指摘しています。環境への適応という観点からいえば、安定している時は保守的となりますが、環境が危機的な状況においては、多様な生命の形態の生存の技術や可能性を担保しておくことが、生存にとって有意になります。その時、人間の社会が、突然変異や特異性を保護するために、諸々の技術やテクノロジーで補い埋め合わせてきたことが指摘されます。これは正常と異常の概念の社会的な意味となります。カンギレムによれば、その古い例は動物を「飼いならす」ことにありました。野生の生存条件から外れた特異な動物を許容し、人間の生存条件のために利用してきたテクノロジーの歴史が、異常と正常の区別に関わることになります。カンギレムは、戦後の状況において「人間があらゆる環境において実存し、抵抗し、技術的・文化的に活動しうる生体」であるかぎりで、多様な特異性が生存できる新しい環境の創造は完成に到達していることも指摘しています。にもかかわらず、機能的な疾患、すなわち精神疾患が新たな病理として問題にされはじめてもいきました。これは、環境に適合していたものが、不適合で危険なものになるときに病理化される特異性として定義されるものです。これをカンギレムは「微視的アノマリー」と呼び、とりわけセリエによる同時代のストレス研究を例に挙げています。つまり、生理学的な定数(心拍、血圧、基礎代謝、一昼夜のリズム、体温などなど)からの偏差は、それ自体において病理的な事実をなすものではないとしても、その偏差が社会生活に不適合となる閾を超えた瞬間に、病理化され障害の原因となりはじめるのです。したがって障害は社会の形態とその適応の条件によって規定されると言えます。そのとき機能上の病気(たとえば高血圧)は形態学的な損傷(たとえば胃潰瘍へ)の原因ともなります。身体的な障害と精神疾患とは重層的に決定されると見なすことができます。ここでカンギレムがストレスという現象に関する生理学の研究を通して提起していることは、たとえば近年にかけて精神疾患の幅が細分化され広く定義されるようになった「PTSD」、「発達障害」、「軽症うつ」といった話題に即して考えることもできるように思われます。
病理や健康の実存的な意味と社会福祉
このように実験医学、生物学、生理学における正常と病理の概念の配置をたどりながらカンギレムは、「病気」をめぐる哲学的・実存的な意味へと議論を進めていきます。カンギレムは一方で、統計学的、生物学的、社会的に構成される病気は、「医者にとって、正常なものと病理的なものの区別を無効にして混同することを奨励することがあっては決してならない」ことに注意しながらも、ある個人が病気となることは、「別の世界へ移行」することであり、「別の人間になった」のであり、「有機体は病気において「別のもの」になる」のだと言います。カンギレムは「病気になること」は、「生命の通常のもろもろのバネにきわめて精緻な仕方で触れる」ので、逸脱や欠損ではなく、「新しい生理学の性質をもつ」というルリッシュの言葉を引用しています。カンギレムにとって健康を特徴づけるものとは、病気になることによって、「正常や規範の変容を許容できる力量をもつこと」となります。すなわち、「人間が真に健康であるのは、その人が幾多の規範を意のままにできるときだけであり、正常以上である(正常を超える)ときだけである。健康の尺度は、有機体の危機を乗り越えて、古いものとは異なる新しい生理学的秩序を創設するある一定の能力である。冗談のつもりなどなしに言えば、健康とは、病気になることができ、そこから回復するという贅沢である」(同書, 197頁)。このカンギレムの議論を、芸術家の身体のあり方に敷衍するならば、芸術家とは、病理的な身体にも接近する特異な身体の可能性を通して、古い規範と戯れながら、それを乗り超え、これまでとは異なる新しい生理学的秩序を創設する能力をもった個体である、と定義することができるのだと言えるでしょう。このように規範となった身体のあり方を乗り越えることができるがゆえに、大いなる特異性かつ健康とを備えた身体こそが、芸術家の身体性だと言えるでしょう。
カンギレムは、このように病理の実存的な意味について述べた後に、生命保険の経済的な成功についても触れています。生命保険は、自らの「正常な(規範的な)」能力よりも優れたものをもたらしうるだろうと。ここで、個体による新しい生理学的秩序の創造の可能性と、社会福祉や保険の結びつきが強調されます。この観点によれば、芸術家の実践と社会福祉の問題が交叉するとき、古い社会への適応(社会的包摂)や治療(セラピー)を超えて、これまでのあり方とは異なる生理学を通して生きることのできる社会をいかに構想できるかが、芸術家の実践に問われていると言っていいかと思います。こう考えるとき、正常と病理をめぐる個人の実存的な意味は、同時に社会福祉をとりまく経済や資本の再分配のシステムによって規定されているという逆説が生じてきます。現代のバイオテクノロジーに結びついた政治や経済の領域を論じたニコラス・ローグによれば、そうした境界は生命倫理学の登場によってすでに変容しています。たとえば健康と富の結びつきについて論じる部分を引用しておきましょう。「健康と富との、一見すると徳を含んだ関係は、政府や私設の財団から投資された研究開発のために、国家の某大な予算を動かし、営利的なヘルスケアや健康管理産業の商取引を動かし、製薬企業やバイオテクノロジー企業の事業、ベンチャー資本や株主資本の流れのための予算を動かすものである」と(ニコラス・ローグ『生そのものの政治学――二十一世紀の生物医学、権力、主体性』檜垣立哉・小倉拓也・佐古仁志・山崎吾郎訳、法政大学出版局、63−64頁)。他方で、私たちは次のような実感もあります。近年の国家による年金の破綻と投資運用によって、一般的に個人の健康が国家によって保障される可能性が著しく不安に晒されてきており、健康のリスク管理が個人に帰されるようになってきているのではないか。さらに低所得者やワーキングプア層にとっては自分が恩恵に預かれない年金や医療保険の支払いによって生活が圧迫されるという現実があるでしょう_。生活保護の不正受給に対する激しいバッシングに見られたように、そのリスクに対する不安やストレスが、社会福祉をめぐっていっそう厳しい相互監視や、障害の幅を広げつつもそれらを等級づけていくための管理的な専門知の要求をもたらしているように思われてなりません。そうした文脈のなかで、果たして芸術に何ができるのか、あるいは障害者の支援に役立てるという理由で、芸術の実践や研究のために予算や時間を費やすことに、どれだけの意義があることなのかが厳しく問われざるを得なくなっている、というのが私が今回のパフォーマンスに際して事前に自ら問いかけたことでした。
3組のパフォーマンスについて
さて3組の舞台パフォーマンスのうち、こうした考えを前提としてもっとも共感を覚えたのは塚原真也さんのパフォーマンスでした。もちろん他の作品も鑑賞しながら多くの感情が引き出されました。砂連尾さんと熊谷さんのコラボレーションでは、身体障害者とダンサーがともに機械を通して身体イメージを共有することの面白さを伝えてくれました。しかも単に身体イメージを共有するというだけでなく、そこで何が起きているのを明確に言葉にするというパフォーマンスになっていました。あえて熊谷さんが介助者の反応を試したりいじめたりしていると思えるような振る舞いをすることで、私たちが善意で障害者を介助するという関係だけでなく、そこにサド−マゾ的とも言えるような複雑な力関係の鬩ぎ合いが現れてくることを、見事に実演してみせてくれました。むしろ砂連尾さんは、ある種の弱い身体性で、熊谷さんの攻めを受けるというコラボレーションで楽しませてくれました。野上さんによる身体障害をもち車椅子で生活する加藤さんとツィスター・ゲームを楽しんでみるというドキュメンタリーでは、事前に芸術家の自意識を消すために中立的なタスクをダンスとして提示するというコンセプトが示されました。むしろ映像では、野上さんの思惑とは裏腹に、ゲームの中で加藤さんの困惑した表情から、私にはダンスを通した共生や社会的な包摂をアートによって試みることの失敗が印象づけられました。そうしたことも含めて、素直に明らかにされたドキュメンタリーを鑑賞しながら苛立ちや困惑の感情が引き出されました。
ここでは特に塚原さんのパフォーマンスを中心に私の考えを述べたいと思います。彼のパフォーマンスは、路上生活者の6割が、精神疾患を抱えており、多くの場合には、やがて他者との接触を断ってしまうことを劇の冒頭で問題提起することからはじまります。貧困・借金の原因に精神的な障害の問題が密接に関わる例を、パフォーマンスの中心に据える着眼は、すでに社会的包摂に失敗してしまった障害者に対して、芸術がどのように向き合うことができるのか、という困難な問いを観客に突きつけるものだと思われます(こうしたテーマはジョー・ライト監督の『路上のソリスト』という映画を思いおこさせました。この映画は LA のスキッド・ローで路上生活を行う統合失調症のチェリストの男が主人公で、彼は新聞記者に励まされてディズニー・コンサートホールで演奏を成功させるものの、また路上生活に戻ってしまいます。精神障害とアートによる社会的包摂の矛盾を描いた作品です)。さらに塚原さんは、中津の自宅近くに住んでいる路上生活者の奇妙な意表をつく身振りを撮影したビデオをもとに、舞台上でパフォーマンスを行います。そして、その対価としてポストカードを劇場で販売し、その売り上げをその男に渡しに行くと言うことがコンセプトの中心にあります。ここでは、プロフェッショナルでない人々に作品に参加してもらい、それを鑑賞することにともなう代価や搾取や経済循環の問題が鋭く提起されているように思えます。
塚原は、子供を抱えたパートナーやヴィッセル神戸でサッカーのプロとして働く弟など家族総出で、このパフォーマンスを構成しました。そこに塚原自身の自伝的な物語が織り込まれます。彼は、大学に入って、サッカーのトレーニングからはドロップアウトし、現在はパフォーマンスに関わる仕事をしているということが語られます。舞台では、子供の時に彼らが兄弟で遊んだワンオンワンのゲームが真剣になされますが、そこには規律を積んで作り上げられたプロサッカー選手の弟の身体性に対して、障害者の想定外の身振りを取り入れた芸術家のパフォーマンスが果たして張り合うことができるのかという問いかけだと思えました。確かに塚原による力士の反則技のように、大きく手を広げる身振りは、目くらましやフェイントになり、上手にプロサッカー選手を抜いてゴールを決める場面もあり、観客から喝采が送られました。しかし、その技もゲーム後半では、弟に見破られ、結局このゲームでは兄は敗北してしまいます。その結果からすれば、芸術家の身体はサッカーのプロの身体に敗北しているし、舞台上では、ダンスによる新しい生理学や身体の創造ということに失敗した結果が、無残に見せつけられるということになるでしょう。ではスポーツ選手になるのではなく、パフォーマーないしは芸術家になるという塚原の試みは全体として失敗だったと言えるのでしょうか。塚原のパフォーマンスが、私にとって感動的かつ共感を呼び起こすものだったのは、そうした失敗や負けも含めて舞台上にあげることで、舞台という空間にはまだ議論する場を生み出すだけのポテンシャルがあることを可能性として示しているように思えたからでした。プロのスポーツ選手は幸運に見えますが、身体障害者になる潜在的予備軍でもあると言えます(たとえば、アメフト選手は脳震盪に、サッカー選手は慢性的に腰痛に悩まされているでしょう)。多くのプロフェッシャルが何らかの身体を商売の道具とし、それが欠損したとき失業者になるリスクや不安やストレスを抱えて日々、生活を送っています。同時にスポーツ施設やスタジアムの建設は、路上生活者を公共の広場から排除するという目的をともなうことがこれまでありました。精神障害を抱えた路上生活者のイメージや身振りは、私たちが将来そうした姿になる可能性に怯えながらも、いつも忘れ視界から遠ざけようとしている身体イメージだといえるかもしれません。むしろそれを忘れたいからこそスポーツ選手の超健康的な身体に私たちは喝采を浴びせるのかもしれません。そうしたことを本パフォーマンスではあらためて考えさせられました。
さらに、このパフォーマンスでは最後に、議論の場としての舞台のもつ潜在的な可能性を占有するかたちで、匿名掲示板の障害者手帳スレッドが機械音声で読み上げられます。このスレッドでは、いかにして障害者認定を獲得して、生活保護や社会保障を得ることができるかについて赤裸々に議論されています。障害者と認定された人々やそうなろうと目論む虚実入り混ざった人々の生々しい意見が、機械化された声で舞台に響き渡りました(放送禁止用語に分類される言葉も大学の舞台で聞かされてヒヤヒヤさせられます)。これもまた日本の障害者と社会福祉をとりまくリアリティの一端に違いないでしょう。
パフォーマンスの後の議論では、時間の都合でこうした問題について十分に深めることができなかったことが残念でした。しかし、今回の試みでは、舞台やダンスやアートの観客という立場から離れて、私たちの生存の共通の基盤となるはずの社会福祉制度にどのような綻びや矛盾があり、それに対する不安やストレスがどのように生理的・精神的に内面化・身体化されて、私たちの生き方のスタイルや態度や気分を左右しているのか。そうしたことを、さまざまな立場から話し合うことができる可能性の端緒に触れることができました。こうした機会のために声をかけていただいた、木村さんをはじめとして、パフォーマーの方々や、参加者の方々に感謝します。